それにしても、これまで文章でだけ知っていて、その光景を想像するしかなかった数々の卓球史のエピソードを、マンガという形に具体化し、広く世に残すことができるというのは、耐えがたい快感である。
今回発売された第1巻では卓球の元となったテニスのさらに元となった「ジュ・ド・ポーム」という16世紀フランスの球技の誕生から、卓球が日本へ伝来して独自の発展を遂げるまでを描いた。登場する人物たちは、セルロイド球を発明したジェームズ・ギブ、ピンポンセットを普及させたジョン・ジェイクス三世、国際卓球連盟を創立したアイボア・モンタギュー、史上最長1ポイント2時間12分のラリーをしたエーリッヒとパネス、あまりに強力なフィンガースピンサービスによって卓球のルールを変えてしまったソル・シフ、卓球を日本に持ち込んだ坪井玄道といった、豪華絢爛てんこ盛りの錚々たる方々だ。
第2巻では日本の卓球が世界に羽ばたく様子から1950年代の卓球ニッポンの黄金時代までを、球聖・今孝、史上最強と言われた藤井則和、そしてミスター卓球・荻村伊智朗を中心として、用具やルールの変遷、名勝負を織り込んで描いた。
どの場面も壮大な卓球物語の1コマであり、卓球に人生を懸けた人々の情熱に満ち満ちている。登場人物たちが残した文章を要所で引用し、台詞にも彼らが手記やインタビューなどで語った言葉をできるだけ散りばめて、マンガに彼らの魂が宿るよう心掛けた。
現在制作中の第3巻では、1960年代になっていよいよ中国が台頭し、必死にそれと対抗しながらも敗れゆく日本の姿を描いている。その後はヨーロッパの卓球が復興しアジアとヨーロッパが拮抗する怒涛の1970年代をピンポン外交、用具の高性能化を交えて描く。さらに1980年代の中国 vs. スウェーデンの死闘と日本での卓球暗黒時代の混迷、そして1990年代の卓球メジャー化への挑戦から2000年代の日本の卓球の再興を経て2016年のリオ五輪での日本の活躍による卓球フィーバーまでを描く。
この壮大な物語の最後は、書き始めたときから決めている。それは、リオ五輪での卓球フィーバー冷めやらぬ2016年11月、深夜の吉祥寺で、久保彰太郎さん(「バタフライ」の数々の卓球用具を開発)と私の会話の場面だ。
久保さんは、自らが作り出した高性能の用具によって卓球があまりにも用具偏重になり、スポーツとして間違った方向に成長してしまったことに自責の念を抱いていた。私はその考えに同意できず反論したが、久保さんの考えを変えることはできなかった。
久保さんが亡くなったのはその翌年の1月だった。生前の久保さんを納得させることはできなかったが、このマンガの最後でもう一度、久保さんに反論させていただく。あなたが作り出した、この素晴らしく高度で面白いスポーツに魅せられて我々はここにいるのですと。
もしも久保さんがこのマンガを読んだら何と言ってくれただろうか。自責の念は変わらなかったかもしれないが、目を細めて喜んだに違いない。第2巻に登場する21歳の自分の姿に「イケメンすぎます」と苦言を呈しながら。
(完)
『マンガで読む 卓球ものがたり1』はコチラ 『マンガで読む 卓球ものがたり2』はコチラ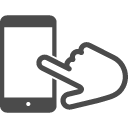 スマホ版に
スマホ版に