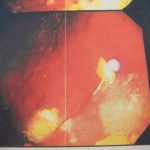ドーサンには日本食の食材はあまり売っていないが、車で4時間かけてアトランタに行くと日本人向けの食材店があり、そこでほとんどのものを買うことができる。ちょっと高いが仕方がない。
そこでみつけた納豆だ。「すべての関西人に捧ぐ日本の伝統食」と書いているが、なんだか関西人は日本人ではないかのようだ。
その名も「うまいねん納豆」。粘りが聞いていそうないい感じのネーミングだ。
粘着性ラバーもこういう名前にしたらどうだろうか。
新参者のキラースピンあたりがやってくれないだろうか。「ひっつく粘(ねん)」とかいって(念もいいかも)。
こういう気をてらったネーミングは昔からTSPが得意だ。桂小五郎(後の木戸孝允)の駄洒落で「桂」と「小五郎」という名前の桂材を使ったラケットを出したことがあるくらいだ。
木戸孝允は幕府を倒して日本を明治維新に導いたひとりだが、なんか荻村伊智朗大先生に似てる。http://ja.wikipedia.org/wiki/桂小五郎
うーむ、納豆からここまできてしまった。これぞ独り言の醍醐味。