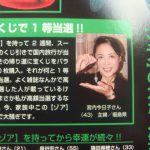ゲストブックに平野と王の決勝試合に関して「促進ルールって何?」とコメントがあったので、得意のくどい口調で説明しよう。
その昔、卓球は今とはくらべものにならないほどラリーが続いた。ネットが今より2cmほど高かったことと、ラケットも弾まず、さらに選手の考え方自体も、リスクのある攻撃は避ける傾向にあったのだ。1936年の世界選手権で、ポーランドのエーリッヒとルーマニアのパネスの試合の最初のラリーが2時間12分続いたことがあった(時間については諸説あるが、もっとも短い時間を書いた)。0-0から1-0になるまで2時間12分だ。その間、首を振ってボールの往復を見ていた審判は首がつり、3人が交代した(この話を友人にしたとき「審判が首を吊った」と聞き違われ「責任とってか?」と驚かれたことがある)。この選手ふたりは、まったく攻撃できないわけではないが、作戦としてそういう粘り作戦で試合に臨んで、お互いに意地になったためらしい。
これでは試合にならないので、そのラリー中にルール委員会で制限時間のルールを検討することになった。ルール委員会をやろうとすると7人いるはずのルール委員がひとり足りないと思ったら、当の試合をしているエーリッヒだったという(ホントかよこの話)。それでエーリッヒ抜きでルール委員会を開こうとするとエーリッヒは「ダメだ」といったらしく、試合をしている台の横でラリー中のエーリッヒを入れてルール委員会が開かれたというおおらかな話だ。
そこで決まったルールが「ゲームが始まって1時間たったらリードしている方の勝ち。もし同点だったらそこから5分間の一本勝負。その5分間でも勝負がつかなかったら両者失格」というものだ。
そして悲劇は起こった。翌1937年の世界選手権女子シングル決勝はアーロンズ(アメリカ)とプリッツィ(オーストリア)で争われたが、先の「促進ルール」によって両者失格となってしまったのだ(それにしても聞き分けの悪い選手たちだ)。これが世界卓球選手権史上、唯一の優勝者なしの記録だ。2001年、国際卓球連盟は、このときのルールが間違っていたと認め、64年ぶりに両者を優勝とする措置をして両者の名誉の回復をはかった。
このような悲劇をさけるため、その後、促進ルールは幾度かの改正を経て、現在のルールでは、1ゲームが10分を越したら「ラリーが13往復続いたら自動的にレシーバーの得点とする」促進ルールに移行することになっている。サーバーは、13往復する前にダメでもともとの捨て身の攻撃をしかけざるをえないわけで、当然、攻撃力のある選手が有利となる。13往復というのは、キリスト教における不吉な数字から来ているのだろう。『ゴルゴ13』の13と同じことだ。攻撃選手の多い現在では促進ルールが適用されることは稀だが、ときどき守備選手がからんだときに促進ルールになることがあるので、審判はストップウォッチが必携だ。今回の場合、平野は攻撃選手なので、促進ルールになることは通常ではほとんどありえないケースだ。いかに平野が異常な粘りを示したか(当然、ラケットを下に振るカットより、上に振るドライブの方が疲れる)、また、平野にそういう異常な作戦を取る以外に勝ちがないと判断させた王の守備の尋常ではない実力がしのばれる。こういう場合、攻撃選手は打ってしまった方がどれだけ楽かわからない。真剣勝負の緊張に耐えながら40往復も50往復もノーミスでドライブをし続けるなど常人にはとても耐えられない所作だ。
なお、促進ルールは、両選手の合意があれば、試合開始から適用することもできる。守備どうしで粘り合いが予想される場合には途中で変えられるより最初からやった方が選手が楽だからだ。よく両方がカットマンだと、選手や審判が試合前に「促進にしませんか?」などと相談する光景が日本中の試合で見られる。守備選手は、普段の練習に「促進ルール対策」を組み入れていることもまた当然のことだ。
促進ルールは、卓球に、回転という要素があるために未だに守備主戦という戦型が存在し、競技領域が小さくボールも軽いために、打法によってはいくらでもラリーを続けることが可能である故に存在し続ける、まさに卓球ならではのルールなのだ。