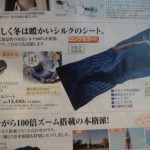年の近い職場の上司がいるのだが、私と持っている服が似ていて、ときどきほとんど同じ服装のときがある。体格も髪型も似ているので、よく間違えて声をかけられる。昨日も見事に似ていたので写真を撮ってみた。まあ、どちらも珍しい服は持っていないので似ることがあるのは当たり前といえば当たり前だが。
月別アーカイブ: 4月 2012
明晰夢
以前、「明晰夢」というものについて書いた。これは夢だと自覚しながら見る夢のことだ。私は最近そういう夢が結構あるのだが、中でも、これは夢だと自覚しながら、ものすごく鮮明に物が見える夢がある。もう、覚醒時と完全に同じ、今こうしてパソコンの画面を見ているのと同じくらいにはっきりとものが見える夢があるのだ。人間に物が見えるということが、つくづく脳によるしざわであり、網膜に映っている物をそのまま見えているわけではないと思い知らされる。
その中でも最近、特に強烈な体験をした。ドルトムントから自宅に帰った晩、時差ボケのためにとても眠いのを我慢して起きていて、やっと寝る時間になったので床に入った。すると、あまりに眠いためかまだ眠っていないのにまぶたを閉じた途端に目の前にとてもはっきりした人形が何やら踊るように動くのが見えたのだ。私は主観的にはその人形にちゃんと焦点を合わせ見ているのだ。「うわ、まだ寝てないのに夢かよ」と思い、面白いので薄目を開けて見た。すると、視界の下半分に現実の景色が見え、上半分に引き続き夢だか幻覚だかが見えるではないか。もちろんこんなことは初めてだ。なんと人間の感覚とは面白いのだろうか。
そんなわけで、どんなに異常な光景を見たとしても、それが合理的に説明がつかないものならば、それは錯覚だと思うという決意を新たにした。
当時の様子
26年前の木村との写真を見つけた。私の記憶の中の木村はこの姿しかなかった。今回会うにあたっては、なにしろ26年も経っているのだから誰だかわからないくらいにみすぼらしく小汚いオヤジになっていることを期待していたのだが、バカバカしいほどの変わらなさ具合で残念だった。変わったのは俺だけかよ。
書いているうちに、木村と親しくなったきっかけをもうひとつ思い出した。私は大学1年の6月に自然気胸という病気になって手術のため1ヶ月間入院をしたのだが、そのときやたらと見舞いに来たのが木村だったのだ。病院は大学からもアパートからも遠かったが木村はゆっくりとどこまでもテクテク歩くヤツで、毎日のように来たのだ。当時発売間もないポールマッカートニーの『タッグ・オブ・ウォー』やクイーンの『ホット・スペース』をテープに録音してきてウォークマンと一緒においてってくれた。ただ、初めて見舞いに来たときの私を見た第一声が「あ、顔が死んでる」というもので、それでなくても気落ちしている私はとてもショックを受けた。看護婦さんも「そんなこと言わないの」とたしなめていた。ともかく第一印象はいやなヤツなのだ。なお、連日のように見舞いに来て何をしていたかといえば、ロクな話もぜずにもっぱら隣の空きベットで昼寝をしては看護婦さんに呆れられていたことも付け加えておく。
旧友との再会
大学を卒業して以来会っていなかった木村という友人と26年ぶりに会った。大学に入学した初日、クラスでの説明会の後、ほとんど最初に会話をしたのがこの男だった。私は人見知りの傾向があるので、なんとなくホームシックと心細い気持ちが混じったような嫌な気持ちになっているところに、この木村に「この後どうしよっか? よし、君んち行こう」と指差されたのだ。
なんてずうずうしいヤツだろうか。聞けば横浜出身だという。横浜とはこんなに不愉快な奴がいるところなのかと思った。顔もなんか嫌な感じだ。まず、初対面なのに敬語を使わないというのが信じられなかったし、東北で育った私は「君」と言われたこともなければ「んち」と言われたこともない(本当は「行こう」といわれたこともないのだが、それまで文句を言っても仕方がない)。ともかくこいつはいきなり私の家に来るというのだ。もちろんこれを断れるはずもなく、ものすごーく嫌な気持ちで家に連れて行ったのだった。
それほど不快な気持だったのだが、ほどなくコイツのなんとも言えないとぼけた風合いと達観した感じに親しみを覚え、数少ない友人となったのだった。これほど第一印象が悪かった友人は他にはいない。高校時代は帰宅部に属し、大学では女友達目当てに園芸部に入っていた。何事にも情熱というものがなく達観しているので、卓球やビートルズに熱中する私を冷笑するような感じだったが、それもまた慣れると心地よいのだった。
都会の人間はなるべく目立たない格好をするのが粋であり、派手な格好をするのは田舎者だということもコイツから教えてもらった。ロックにも詳しく、部屋の壁にレコードジャケットを何枚も飾ってあったのを私も真似をしたものだった。XTC、ニューオーダー、U2など、パンク・ニューウエイブ系音楽の私の先生だった。彼の部屋には、ロッキングオンやミュージックライフといったロック雑誌、いがらしみきおのマンガなどがたくさん置いてあり、私はそれによってサブカルチャー全般について興味を抱くようになった。そのにじみ出る落ち着きと物事に動じない態度からか、仲間の誰よりも早く彼女ができ、しかもそれも先輩から言い寄られたというのだから、我々は驚愕し尊敬をしたものだった。
卒業後、私が大学院に進んだのに対して木村は就職してしまったことと、達観しているだけあって常にそっけないヤツなので、なんとなく疎遠になり、つい26年も会わないでしまった。
久しぶりに会ったものの、自然と卓球の話になった。「卓球やるヤツっていつでもどこでも素振りしてるじゃん」と言われて可笑しくなった。木村には中学だか高校だかの同級生に天野という卓球狂がいて、とにかくいつでもどこでも「シャッ」と素振りをしていたそうだ。「しかも迷いがないよね」と言う。ゴルフをする人たちの素振りが何かフォームを確認したり修正する目的で「迷っている様子」なのに対して、卓球人のそれは「迷いがない」のだそうだ。もちろんこれはバカにしているのだ。考えてみると、ラケットを持っていなくても素振りをするのは卓球人ぐらいだろう。「型」が目的になっているからだ。これは雑誌にも書いたが日本の卓球の悪習だと思っている。また、木村の母親が昔卓球をしていた人で、家族で温泉で卓球をするときに、いきなりネット際の角を狙ったりして「卓球部ってのは空気の読めないセコいことをするよね」とも言われた(メニューを使ってコースを示してもらうと「フォア前」のことだった)。26年前の私ならむきになって反論するところだが、今回は一緒に笑った。卓球とはそういうスポーツなのだ。