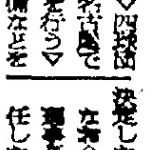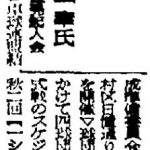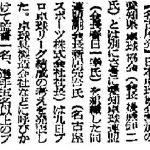グランドキャニオンには飛行場があって、そこで着陸をして今度はバスで移動をする。
マサーポイントと呼ばれる絶景のところがあり、そこで巨大な景色を見られるはずだったのだが、なんと雨が降っていて対岸が見えない。対岸まで39kmもあるという途方もない大きさの谷のはずなのだ。近くの下のほうは見えるのだが、視線を水平にすると何も見えない。なんとも残念だ。ちなみにグランドキャニオンの長さは400kmだというが、これはどうせ見渡すことはできない大きさなのだからどうでもよい。
本当はもう一ヶ所回るツアーだったのだが、雨のため危険な状態なので、この一ヶ所で2時間も過ごすことになった。過ごすといっても、写真の通りほとんど何も見えないので、土産物屋を見たりコーヒーを飲んだりして時間をつぶした。
日本から来た客の中には、ヘリコプターで谷を回るツアーに参加を予定していた人たちもいたが、それもすべて中止だった(料金は返すと言っていた)。その落胆に比べればマシだなと思うことにした。
そういうわけで、雨のグランドキャニオンはさっぱり面白くなかった。