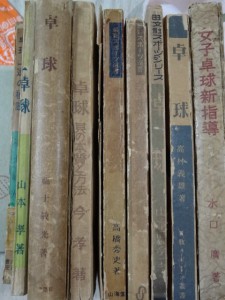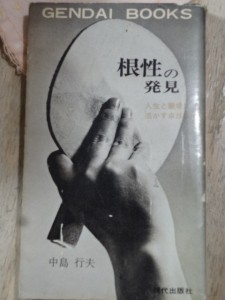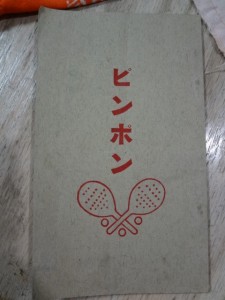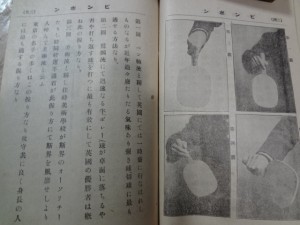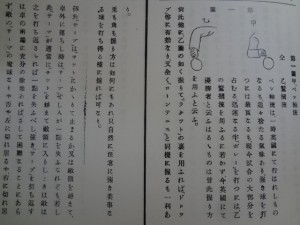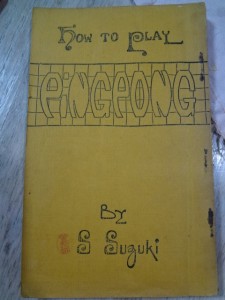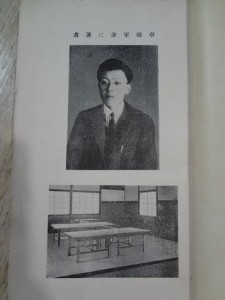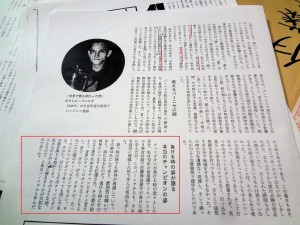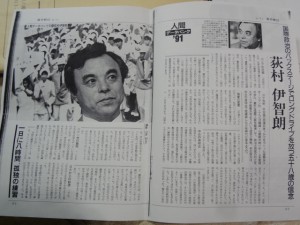昨日、漫才番組を見ていたらちょっとひっかかるネタがあった。チュートリアルというコンビなのだが、ボケの方がバーベキューをするときに串に刺す具の順番についてやたらとこだわり「近代バーベキューの父トーマス・マッコイによれば」とか「その刺し方はニューヨークスタイルだ」とか言ったりして笑いを誘っていた。
この「近代バーベキューの父トーマス・マッコイ」というフレーズがあまりにももっともらしいのでとてもおかしかった。よくそんなこと思いついたものだと思ったが、実在しそうな名前なので、有名人からとったのだろうと思ってネットで調べてみて驚いた。本当にいるのだ「近代バーベキューの父、トーマス・マッコイ」が。そのサイトから引用しよう。
「近代バーベキューの父」とよばれるアメリカの学者。BBQの串の具の順番の研究で大変に有名。栄養のバランスがよくヘルシーで飽きのこない並びを多く提唱した。このような並び順は現在では「ニューヨークスタイル」と言われている。
<ニューヨークスタイルの例>
ピーマン・シイタケ・エリンギ・タマネギ・ホタテ・・・現代の流行を表す際に多用される組み合わせ。野菜が多くヘルシー
ピーマン・タマネギ・タマネギ・タマネギ・タマネギ・タマネギ・オニオン・・・玉葱ばかりだが玉葱好きにはたまらない串
ピーマン・ウインナー・鶏肉・トウモロコシ・ホタテ・・・マッコイが提唱したNYスタイルの定番。魚肉の比率が多いが比較的ヘルシーで飽きの来ない並びになっている
ピーマン・エリンギ・トウモロコシ・トウモロコシ・鶏肉・なすび・・・おなすでシメることで、近代バーベキューの発展の可能性を感じさせる一串。
<ダメな例>
肉・ピーマン・タマネギ・肉・ピーマン・タマネギ・・・単調にて愚鈍。こんな串はいまどき収容所でもつくられていない
ピーマン・ウインナー・トウモロコシ・レンコン・エリンギ・エビ・・・NYスタイルを意識したものだが、ウインナーとエビという組み合わせがダメ。トウモロコシとレンコンで追い討ちをかけている。
どうだろうか。なんか、冗談ではないかと疑わせるフレーズもあるが、どうも本気のようである。その漫才では、具の並びを含めてかなりの部分、ここに書かれている通りのことを言って会場の笑いを誘っていたのだが、バーベキューを真面目に研究している人たちからすると「貴様ら何が可笑しい!」と腹が立ったのではないだろうか。もしかすると卓球についてのノウハウも、そのままリアルに言うと漫才のネタになったりしないかと不安になった。
それにしても、漫才でもオチに使っていたが、玉葱が5個続いた後にオニオンとは・・・いったいどういうことなのだろうか。ギャグとしか思えないのだが、トーマス・マッコイの記事は2006年のサイトにも書いてあるし、やはり本気なのだろう。いやはやいろいろな人がいるものだ。私も負けてはいられないと正月から決意を新たにした。屁理屈をつけて「卓球の試合の美しいスコア」でも提唱するか!それだけを軸にすべての試合を論評したりして。「8-6というスコアがダメ。こんなスコアが許されたのは70年代まで。今どき小学生でもこんなセンスのないスコアにはしない」とか。
と、ここまで書いてから不安になってまたネットで調べると、チュートリアルのこのネタは2006年以前からやっている古いもののようで、どうもこのトーマス・マッコイは実在せず、彼らの創作のようである。少なくとも実在する証拠は見つからなかった。さすがにそうだよなあ。玉葱、オニオンじゃなあ。