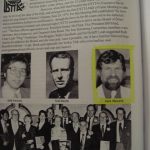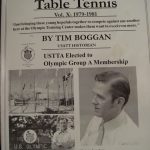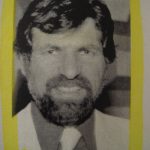ジャックが「他に聞きたいことは?」と言うので、ソル・シフのフィンガースピンサービス(以下FSSと略)について聞いてみた。FSSというのは、サービスを出すときに指で思いっきりボールに回転をかけてさらにそれをラケットめがけて激しくぶつけ、とんでもない方向にとんでもない量の回転がかかるという伝説のサービスだ。
1938年に日本に来たサバドスとケレンに初めてそれを出された日本人選手は、あまりのボールの変化に、目の前で消えたとしか思えなかったという。それでほとんどすべてのボールを触れもせずに負けたのだ。
FSSが世界に登場したのはその前年の1937年のバーデン大会だ。この大会で、アメリカの選手団は、会場のオーストリアに向かう船の中でこのサービスばかりを練習し、ほとんどそれだけで男女団体に優勝したという。これが史上唯一のアメリカの団体優勝である。その男子チームの中心人物こそ、伝説の男、ソル・シフ(Sol Schiff)なのだ。
もちろん、FSSはただちに禁止され、その後使う者はなかったが、後年、ソル・シフが余興で見せるFSSたるやもの凄く、現役選手たちのほとんどがレシーブできなかったと言われる。
ところがジャックの話は意外なものだった。彼は、実際にシフがフクシマという日本代表選手にFSSを出す余興を見たが、フクシマはほとんどミスなく返したという。逆に、フクシマが当時のルールに則ったサービスを出すと、それをシフは返せなかったというのだ。私はフクシマという選手は聞いたことがなかったので「タカシマではないか」と言うと「カットマンのタカシマはもちろん知っている。そうじゃなくてペンホルダーのフクシマだ、知らないのか?」と言う。家に帰ってから調べてみると、福島萬治という選手が1963年のアジア大会に出た記録があった。そういえば聞いたことがあるのを思い出した。ともかくそういうことで、高島さんが受けて20本連続でミスしたと、私が高島さん本人から聞いた話とは真逆の印象の話である。
おそらくこれは、福島がなんらかの理由でFSSを取り慣れていたものと思われる。そうとしか考えられない。実際、高島さんの話だと、今でも余興でFSSを出す人はヨーロッパにいて、慣れていない人は全然返せないのだそうだ。とにかくラケットの動きと関係ない方向にボールが回転しているので、とんでもないミスをしてしまうらしい。1975年のカルカッタ大会で”雨漏りによるゲーム中断がなければ優勝していた”といわれるミスター・カットマンがそう言うのだからこれは間違いない。
それにしても受けてみたい。本場のフィンガースピンサービス。誰かそういうツアーの企画してくれないもんか。『フィンガースピンサービスで味わうオーストリア7日間の旅』とか。タクシー代をケチって間違ったバスに乗って終点までいくような奴が3、4人参加するかもしれないぞ。