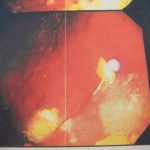「良心的」という言葉をめぐって人形俳句写真の義姉としばらく議論をしていた。
議論の発端は、義姉がこの言葉を使ったことだったが、考えてみると私は以前からこの言葉に縁があった。
以前、他人に理解できない理由で怒り出す、ちょっと異常な同僚Aがいた。その同僚と別の同僚Bがある装置の予約について口論となった。その装置は混んでいるので、使う日の使う時間帯だけ予約を入れるのが普通なのだが、同僚Aはさすがにおかしいだけあって「いつ使うか分からないから」という理由で、一週間まるまる朝から晩まで予約を入れてしまった。
これには当然、他の使用者たちが騒然となり、同僚Bが代表して同僚Aを説得にかかったのだった。私は俄然楽しくなって、二人の口論に聞き耳を立てた。
口論の中で同僚Bが「使う時間に対して予備としてどれくらい多めに予約するかは、使用者個々の・・」と言いかかったときだった。同僚Aが突然ブチ切れて「『良心』なんて言ってみろ!ブン殴るぞB!」と絶叫したのだ。「良心」という言葉に脈絡なく反応して激昂するAがなんとも可笑しく、それ以来、この言葉はお気に入りとなった。