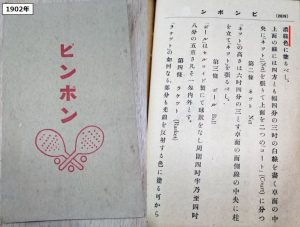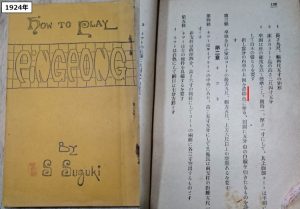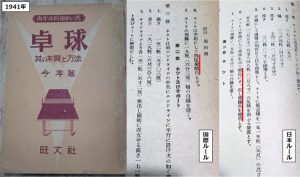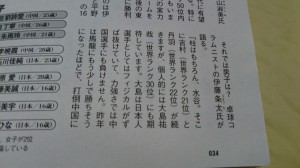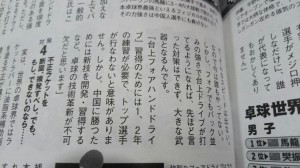私は野球には興味がないのだが、『アンビリバボー』というテレビ番組で、野球に関して見事な捏造をしていて非常に面白かった。
広島カープの黒田というピッチャーが、2006年に他球団へ移籍ができる権利を得たときに、ファンが、試合中の黒田に向けて観客席の横断幕でメッセージを送ったのだという。
その文面は
我々は共に闘ってきた/今までもこれからも・・・/未来へ輝くその日まで/君が涙を流すなら/君の涙になってやる/Carpのエース黒田博樹
というもので、番組ではこれに
「本当は残留して欲しい。だが、たとえ移籍しても最大限のエールで背中を押してあげたいというファンの切なくも熱い思いだった」
とナレーションが入れられた。それに続いて黒田本人も「こういう経験はなかったので嬉しかった」と回想するシーンが入っている。

この横断幕のメッセージのいったいどこがそう読めるだろうか。
直接的には移籍して良いとも残ってほしいとも書いていないが「これからも共に闘う」とあるのだから、どちらかといえばこれは「残ってほしい」だろう。
これを「移籍しても応援する」と読めるのは考え過ぎの人か頭がオカしい人である。仮に本当はそういう意味だったとしても、この私がわからないようなあいまいなものがメッセージとして機能するわけがない。
ネットで検索してみたら、案の定、これは「残ってほしい」という横断幕だった。
http://blog.goo.ne.jp/radiota/e/5482a9bce757e68b61e38fc14e5ff6d9
書いた当事者である私設応援団連盟会長も、当時これを読んだ黒田本人も残留の願いと捉えている。だから番組内の黒田の回想も、その意味で「嬉しかった」と言っているのをつなげているだけなのだ。
どうせ誰も気がつかないのだから事実などどうでもよいのだろう。調べればすぐに嘘だとわかることでも全然気にしないで放送するのだ。
超メジャーな野球ですらこんなデタラメを放送されるのだから、新参者の卓球などどんな目に合うかわかったものではない。
油断はできないぞと改めて思った次第だ。