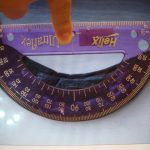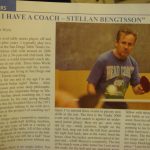「自分とは何か」といっても、よくある「自分探し」の話ではない。
『シックス・デイ』というクローン人間に関する映画をDVDで見た。中学生のとき藤子不二夫のSF短編『俺と俺と俺』を読んで以来、非常に興味を持っていた「自分とは何か」を考えさせられるテーマだ。
自分とは肉体、頭脳、記憶、意識のどれだろうか。多分、肉体だという人はいないだろう。おそらく、記憶と意識をもった脳こそが自分だと誰でも思うだろう。それでは、上記の映画やマンガにあるように、なんらかの方法で脳を記憶ごと複製できたとしたら、それは自分だろうか、それとも自分とは別のものだろうか。たぶん、「それは自分ではなく複製にすぎない」と言うだろう。しかし、なにしろその複製は、自分と同じ記憶を持っているので、複製本人としてはまさに「自分」のつもりなのだ。肉体が本物と違ったところがあったとしても、「肉体そのものは自分を決める重要なものではない」ことは先に認めているわけだから、それは判断基準にならない。だからその複製は敢然として自分であることを主張するだろう。
実はこの二人はまったく対等だというのが私の考えだ。
次に出てくる疑問。では、本物を殺して複製を聞かし続けても、それは自分が生き続けたと考えてよいか。これも、感覚的には抵抗があるが、実はそれで良いというのが私の結論だ。
なぜなら、我々は毎日それをやっているからだ。それは寝ることだ。寝ることによって、私たちの意識はそこで一度途切れる。翌日目が覚めたときに昨日の自分と同じだと感じるのは「記憶」があるためにすぎず、その絶対的な証拠ではない。
仮に科学が発達して、ある人が寝ている間に複製を作ったとしても本物との間に優劣をつけることはできない。つまり、自分が自分である保障はどこにもないのだ。毎朝目覚めているのは、自分の記憶を引き継いだ他人であると考えてもよい。それでは昨日の自分はどうなるのか、死んだと考えていいのか。その通り。眠るということは、意識がとぎれるという意味で、死んだのと同じことであり、だから我々は毎日死んでいるのだ。
なんと自分というもののあやふやなことよ。自分探しもへったくれもない。
と同時に最近思うことは、毎晩死んでは記憶を引き継いで目覚めることを、これを「生きている」と考えてよいなら、自分が本当に死んでも、友人やら子孫やら誰かが自分のことを覚えていてくれる人がこの世に残っていれば、実はそれもある意味で「生きている」と言えなくもないということだ。「○○さんは私たちの心の中に生きている」というセリフが、比喩ではなくて本質的な意味で事実と考えることもできるわけだ。
この話、何度か人に話したことがあるのだが、どうにも、うまく表現できたためしがない。