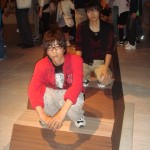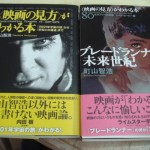連休中に、仙台市営の施設で「トリックアート」という展示があったので息子たちと行ってきた。メインは立体感のある絵なのだが、なかなか面白かった。だいたいこういうのは写真で見ると面白そうだが実際に見ると錯覚が起こらないものだが、これは実際に見ても不思議な感じがした。たかが絵でよくここまで錯覚をおこさせられるものだ。
右端の写真は、床に書いてある絵の上でしゃがんでいるだけであり、実際には台はない。
次男のギャグ
今朝は雨が降りそうだったので、息子たちを学校まで車で送った。
その車中「お前たちはどんな大人になるのかな」というようなことを言うと、次男が「25歳ぐらいまで家でパソコンしてて、銀行に行ってデカいことする」と言った。なかなか面白いじゃないか。私が誉めると次男はさらに「先生がスキマ時間を上手く使えって言うから、スキマ時間使ってゲームする」と言ってゲーム機を立ち上げる音がした。その後、しばらく静かだったので声をかけると、ぐったりした声で「酔った」と言った。ダメだこりゃ。
「ヤンキー」
先日、息子たちが見ているテレビを見ていたら、スマップの中居が元ヤンキーだということで「元ヤン」などと言われていた。
息子たちもことあるごとに友だちなどのことを「あいつはヤンキーだ」なんて言ってる。
私はどうしてもこのヤンキーという言葉になじめない。初めてこの用法を聞いたのはもう20年以上前の学生時代のことだが、ヤンキーとはもともとあった言葉で、アメリカの白人のことなのだ。それがどういうわけで日本の不良少年のことを指すことになったのだろうか。少しは似ているのならともかく、完全に根も葉もない話である。こんな無秩序な転用はどうしても認めるわけには行かない。
息子たちが「ヤンキー」と言ったら、すかさず「ほう。そいつ、アメリカ人なのか?」と言って話の腰を折ることにしている。そのたびに息子たちは「いや、アメリカ人じゃなくて日本人の不良」と答える。我が家の「ヤンキー撲滅」に向けて粘り強く続けようと思う。
それにしても不良という言葉もよくよく考えると面白い。なにしろ「良くない」ってんだから随分とまた直接的なものだ(笑)。でも、良くはなくても普通なら問題ないのではないだろうか。そういえばちゃんと「ワル(悪)」という言葉もあるではないか。だから不良は「普通だから問題ない」、問題児は「ワル」と呼ぼう!古いといわれること間違いなしだ。
世界ろう者卓球選手権大会
東京で行われているろう者の世界選手権で女子が大活躍したようだ。
女子団体、女子ダブルスで優勝、女子シングルスでは日本人同士の決勝で上田萌選手が優勝したようだ。
ウエブサイトのトーナメント表は情報があまり更新されず見づらいが、ともかく素晴らしい結果だ。
http://2012wdttc.org/jp/?p=1643
嬉しいなあもう。
ポーカーゲーム
学生時代のギャンブルということでは、ポーカーゲームがあった。私はたまたま喫茶店などにあるテレビゲームでのポーカーをお金を使わずにやれる環境があって、そこである実験をしたのだ。
まずルールを説明しよう。最初に5枚配られて、変えたいカードを指定して変えて、ワンペアとかスリーカードとか役ものが出来ればそれに応じた点数が入るルールだ。しかしこれだけではあまり面白くない。醍醐味は次の勝負だ。役が出来ると、次の1枚のカードが7より大きいか(ハイ)小さいか(ロー)を賭けて、何回でも当たるごとに倍になり、外れるとすべて失うハイ&ロー勝負という仕組みがあり、それがこのゲームの醍醐味なのだ。だからワンペアという最低の役でもこの勝負で3回当たれば8倍の点数がもらえるという仕組みだ。ちなみに7が出たらどちらに賭けていても外れだ。みんなはこのハイ&ロー勝負に異常に熱中していて「ハイハイと来たから次はローだ」とか「ツーペアのときはローの確率が高い」とかさまざまな「法則」を探そうと血眼になっていた。
そこで私の興味は、このハイ&ロー勝負のカードが本当のカードゲームのようにランダムに出ているのか、それともコントロールされているのかだ。ランダムに出ているのなら、こちらの選び方によっては運がよければ勝つかもしれないが、あらかじめ勝敗が決められていて、出るカードはその勝敗とつじつまを合わせているだけなら考えるだけ無駄だ。
そこで私は巧妙な方法を思いついた。このゲームは、一応は本物のカードゲームを模しているので、一回の勝負中には同じカードは二度と出てこない。だから、もしハイ&ロー勝負のカードが本当にランダムに出ているのなら、最初に配られるカードを記録していれば、ハイ&ロー勝負のときのカードのハイとローの確率がわずかに有利に予測できるはずなのだ。
たとえば極端な例だと、5枚配られたカードが5枚とも7より小さく、5枚を総入れ替えして配られた5枚がまた5枚とも7より小さかったとすると、52枚のカードのうち、7より小さいカードをすでに10枚も見たわけだから、残りは7より大きいカードが24枚、7が4枚、7より小さいカードが14枚となり、ハイに賭ければ勝つ確率が24/42になって50%を越えるのだ。こういうケースだけ何百回分も集めて勝率を計算すれば、必ず勝率は50%を越えるはずである。
このように、配られたカードのハイ&ローのすべてのケースについて表を作っておいて、勝負をしながらその表に勝ち負けを記録していった。これで何日か統計をとったところ、見たカードにまったく関係なく常に勝率は50%以下だったのだ。したがって、ハイ&ロー勝負のカードはランダムに出ているのではなく、こちらがどちらを選ぼうとも勝敗が決まっているということであり、こちらの自由選択は見せかけだけのものだということだ。これでは勝負をするだけ無駄である。
それを確認したことをもって私はゲーム機に勝ったことにして、その店に通うのを止めたのだった。もちろんお金は1円も使っていない。
パチンコ
震災関連のテレビ番組を見ると、せっかく政府からお金をもらっても何もすることがないからパチンコに使ってしまったなんて話を福島の人たちがしていた。そういえば私の近所でも、津波の後で一番早く営業を再開したのはパチンコ屋だった。それでなくても震災で家やお金や仕事を失くした人たちが、わざわざパチンコをしてさらに金を失くすのだからなんとも哀れな話だ。
ギャンブルで一番儲ける方法はとても簡単だ。やらないことだ。ギャンブルをやれば期待値はマイナスなのだから、期待値がゼロ、つまりやらないのが一番儲かるのだ。私はギャンブルをやっている人たちがいかに大枚を失っているかを想像し、自分はその分だけ彼らより相対的に儲かっていると思うことで喜んでいる。パチンコで毎日何千円も失っている人たちに比べれば私は何もせずにその分だけまるまる儲かっているのだ。その差額たるや、ガソリンの値段の上下やスーパーの安売りなどの差どころではない。
とはいえ、実はわたしもパチンコをする人たちの気持はよーくわかる。大学3年までは私もときどきやっては損をしてそれこそ止められなくなっていたのだ。あるとき、卓球部の後輩から「必ず儲かる打ち方」を教わり、それで立て続けに何十万円か儲けて、パチンコと関わったことによる収支がプラスになったことを確認し、そのまま永遠に勝ち逃げするべく二度とやらないことにしたのだ。
ちなみのその打ち方とは、回転している役物の穴が下に来たときだけ3発打って次の機会まで数秒待ってはまた3発だけ打つというただそれだけだ。こうすると、その穴に入るまでに使う球が通常の数分の1に抑えられるため、それによってその機種が想定している出球率をはるかに越えてしまうために、ほとんどどの台に座っても必ず儲かってしまうのだ。この打ち方はインチキではないが、誰でも儲かってしまうという点でずるいといえばずるい。こういう攻略を許してしまったこの機種の設計ミスにつけ込んだ打ち方なのだ。当然、この機種がなくなるのは時間の問題だから、卓球する間も惜しんでパチンコをしたものだった。「必ず勝つと分かっていたら面白くないんじゃないか」という人がいそうだが、とんでもない。楽しくて楽しくて胸が高鳴り、まさに人生の勝利者のような気持ちがしたものだった。今でもときどきそのときの夢を見るほどだ。ああいうボロ儲けをすると、普通のフェアな条件でのパチンコなどバカバカしくて二度とする気にはならない。
あれがなければ、私は負けを取り返そうと今でもパチンコやスロットマシンをやっていたかもしれない。運がよかったと思う。震災で仕事や家を失ってさらにパチンコで金を失っている人にはかける言葉もない。結局は多額の寄付や賠償金がパチンコ屋に流れているということなのだ。パチンコ屋がどこよりも早く復興したのもうなづける。
カラオケ
4連休の初日である昨日は、久しぶりに家族でカラオケに行ってきた。久しぶりといっても、前回行ったのはまだ子供が会話もできない年齢の頃だから、今回が初めてのようなものだ。子供たちも中高生になって友だちとカラオケに行っているようだし、私は私で最近は好きなロックが歌えるということで珍しく動機が一致し、行くことになった。
行ってみると、歌いたい曲が沢山あって嬉しくなった。さっそく歌おうとすると子供たちが「ジャンケンで順番を決めよう」と手を出した。「なぜそんなことをする?」と聞くと「公平になるように」だそうだ。「公平って、お前たちは先に歌いたいのかそれとも後に歌いたいのか」と聞くと「後に歌いたい」と言う。「じゃ俺が先に歌うからジャンケンは要らない」と言うと「信じられない」なんて言っている。先に歌うのが恥ずかしいと言うのだ。
わが子ながらなんとも小さいことを言うものだ。無論、私もそういう気持はわかる。しかし他人は自分が思うほど自分のことを見てはいないし、理屈で考えて恥ずかしくないことを恥ずかしいと思うのは幼稚なのだと私は幼少時から思っているので、こういうときは自分の感情に反して意地でも堂々と振舞うようにしている。たとえば今でも、講演会のときなどで、前の方に座るのが恥ずかしくて全員が後の方に座っているときでも私は一人でずかずかと歩いて行って一番前の中央に座る。するとそれを見て「恥ずかしさの防波堤」ができたとでも思ってか他の人たちもおずおずと臆病な羊のように私の後の席を埋めだす。二十歳どころか四十にも五十になってもこんなことで時間を費やしたり主催者に「前に詰めてください」と言わせたりしているのだ。しかし私も実はとても恥ずかしいのを意思の力で無理やりやっているのでかなり緊張していて加減が分からない状態になっている。その結果、講演者の席に座って「そこはちょっと・・」と主催者から注意をされることもあるくらいなのだ。それにしたっていくらなんでもカラオケで最初に歌うなんぞは屁でもない。
それで歌ったのが前から歌いたくてずっと練習していたピンク・フロイドの「あなたがここにいてほしい」だ。これがイントロが素晴らしく長く、歌い出すまで1分20秒かかるのだが、カラオケでもちゃんと本物と同じく長いイントロだった(http://www.youtube.com/watch?v=IXdNnw99-Ic。あまりに歌が始まらないので子供たちが「お父さん、何これ?何?」とうるさい。次男など「歌がないカラオケなの?」なんて言ってる。あるかそんなの。
イントロが長いと書いたが、ピンクフロイドの曲としては普通である。ひどいのになると歌い出すまで9分近くかかるのもあるのだ(「狂ったダイヤモンド」http://www.youtube.com/watch?v=1N8BYNMMjqU&feature=related。さすがにこれのカラオケはなかったが、もし歌ったらブーイングだろう。
私が続いてスミスの「心に茨を持つ少年」を歌おうとすると、子供たちが冷たくこわばった顔をした。連続で歌うのは絶対にやってはいけないタブーで「友達がいなくなる」行為だというのだ。他人が歌っているスキに自分の曲を5曲も6曲もぶち込んだり、他人の入れた曲を横取りして歌ったりする我々のような考えは彼らにはないようである。
最近は切れる子供も少なく凶悪犯罪も激減し、子供がすっかり大人しくなったという統計を実感した瞬間であった。いいヤツばかりでよい世の中になったものだ(どうしても皮肉っぽく響くが皮肉ではなく本当にそう思う)。
缶コーヒーのおまけ
ドルトムント帰還祝い
昨夜は私のドルトムント帰還祝いという、いかにもとってつけたような名目でいつものメンバーで飲んだ。
飲んだ店は百人屋台という店で、屋内なのにまるで屋外にいるかのような凝った飾りつけの店だ。我々が居座ったところは「空中座敷」と言われるところで、片面が屋外に面していてビニールシートが張ってあるだけのところだ。夏はビニールシートを取るので開放感があって楽しそうだ。
トイレに行くと、思いっきり昭和の広告が貼ってあってしばし見入ってしまった。
連休中のためか店内にほとんど客はおらず、7時から1時まで6時間もダラダラと飲み食いをしたのだった。私は何事も過剰でしつこくいく性質なので、こういうやり方が好きなのだ。
町山智浩
2ヶ月ほど前、ふと近所の本屋で手に取った本で、久しぶりに素晴らしい作家と出会った。町山智浩という人だ。『映画の見方がわかる本』というのだが、これまでに読んだどんな映画解説本とも違う、本当に面白い本だった。
簡単に言えば、それぞれの映画の構想段階の資料や関係者の発言などを根拠にして、作者の意図や本当の意味を探ることで、映画を楽しむことを助ける本である。往々にして芸術家は自分の作品を説明することを嫌い「見た人が好きなように感じてくれればいい」などと言うし、それを真に受けて「芸術を鑑賞するのに余計な知識は不要でありそれは本来の楽しみ方ではない」という人がいる。本来もクソもない。その方が面白い人はそうすればよいだけのことだ。私は断然その方が面白い。作者の意図や前提となる事実を誤解したまま感動して何になるというのだ。
たとえば『2001年宇宙の旅』はいろいろと哲学的で難解なことで有名だが、実は全然そうではなく、すべてのシーンには明快で即物的な意味があったのだ。猿が進化するきっかけとなったモノリスという黒石板は神秘的なものではなくて宇宙人が作った人工的な「装置」だし、ボーマンが宇宙で18世紀フランス風の部屋で食事をするシーンは、宇宙人がボーマンをもてなすために地球の様子を真似て技術的に再現した部屋なのだ。こういった本当の意味を説明するナレーションや実際に撮影されたシーンが沢山あり、それはもう議論の余地がないのだ。それをキューブリックは編集の段階で次々と情報を削ってわざと意味が分からないものにした。理由は「映画のマジック」のためだ。わざと分かりにくくした方が、見るほうがあれこれと深読みをしてくれて評価が高まると思ってのことなのだ。だから、分かりにくくなった部分をトンチンカンな解釈をして論じてもまったく無意味なのだ。
こういったことを『タクシードライバー』『時計仕掛けのオレンジ』などといった名作について事細かに論証していくという、そういう本である。
さて、それだけならただの「映画マニアのための裏話本」にすぎないようだが、そうではない。これらの裏話を通して町山の映画に対する思いや言いたいことが伝わってきて、読者はそれに感動するのだ。映画評論に限らずあらゆる評論は、作品の解説のためだけにあるのではない。評論自体がその人の表現であり作品なのだ。どんなに詳しい映画の裏話を仕入れたところで、誰も町山のようには書けまい。まさに帯に書いてあるようにこの本は「町山智浩以外には誰も書けない映画論」なのだ。特に、ポール・シュレイダーがなぜ『タクシー・ドライバー』を書き、スコセッシがなぜそれを監督したかを解説するあたりは白眉である。
それにしてもこんなに優れた評論家を今まで名前も聞いたこともなかったとは。損したような気になる一方で、新たな楽しみが増えて嬉しいような気もする。
昨夜、YouTubeで初めて顔を見たが、そのパフォーマンスも素晴らしかった。
http://www.youtube.com/watch?v=Xll4jPQ6c-8
もう「一生ついていきます」という気分だ。