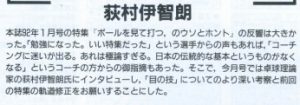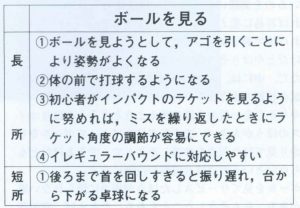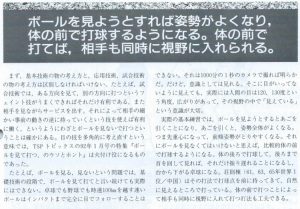昨日終わった全日本の女子シングルスの決勝の3ゲーム目で、非常に奇妙なマナーが見られた。
伊藤が大量にリードして、スコアが10-0になって、あわやラブゲームになりそうなところで伊藤のサービスになった。ここで私は、最近テレビで取り上げられる卓球のトリビア「ラブゲームで勝ってはいけないという暗黙のルール」を思い出し、やるんだろうなあと思った。隣にいた佐藤祐も「さあどうする」とつぶやいたので同じことを思ったのだろう。
直後、伊藤はサービスミスをして、会場に拍手が沸き起こった。
なんだろうこれは。そもそも卓球界にそんな「暗黙のルール」はない。暗黙であるかぎりルールではあり得ないから、言うとすれば「暗黙のマナー」だろう。
しかしこれのどこがマナーだろうか。もちろんこんなマナーは前からあるものではない。スポーツである以上は、どんな状況であっても全力で点を取りに行くことこそが相手を尊重することでありマナーであるに決まっている。
それをいつの間にか中国選手がやるようになっただけのことだ。0点で勝って相手の面子を潰さないようにとの配慮らしい。しかし誰にでも故意とわかるサービスミスをしてもらって、ほんの少しでも面子が保たれるだろうか。
文化の違う中国人はそう考えるのかもしれないが、日本人の感覚ではそうではあるまい。むしろ絶対に逆転されないという慢心の表れとも言えるから話は逆のはずだ。もしも、10-0になった途端、勝っている方がレシーブからロビングを上げたら、相手はバカにされていると思うだろう。故意のサービスミスやレシーブミスは問答無用で相手に点を与えるのだからそれより酷いのだ。
記録に残るスコアが11-0では可哀そうだというなら、中国国内リーグだけ1-1から試合を始めればよいだけだ。
世界一強い中国選手がやるからといって、不合理なマナーに日本人が付き合う理由はどこにもない。
ましてそれをトリビアだなどといって「タオルで汗を拭くのが6本毎」と同じレベルで「0点で勝ってはいけない」とテレビで宣伝するなどとんでもないことだ。
おかげで観客は拍手をして伊藤のサービスミスを讃えた。しかし、讃える理由などない。10-0から1点を与えても伊藤には何のリスクもないし、暗黙のルールだと思っているから機械的にやっただけだ。
逆に、男子シングルス決勝の4ゲームめ、10-1からのラリーで張本のサービスがレットとなった。このとき張本は、ボールが自分の顔に当たったことを自ら審判にアピールし、審判はこれを受け入れてスコアを10-2に訂正した。フェアだ。しかし、ここで観客はまったくの無反応だったのだ。
静まり返った会場で、審判の声「レット、10-1・・・・・10-2」という声も聞こえていて完全に状況はわかっているはずなのにだ。これこそ賞賛されるべきなのに。
恐らく観客の伊藤への拍手は、マナーを讃えたのではなく、テレビで見たトリビアの実演を目撃できたことが嬉しかったことの表れなのだろう。
卓球界のマナーとして昔からあるのは、審判のミスによって自分に点が入り、それを審判にアピールしても受け入れられなかったとき、次のボールをわざとミスするというものだ。やる人もいればやらない人もいるが、勝負を決する大事な場面でこれをやる者は、万雷の拍手を受ける。
誰だった忘れたが(ボルだったかサムソノフだったか)、マッチポイントを握られている状態で、相手のボールがオーバーし、審判はその選手に点を入れた。しかしその選手だけは相手のボールがエッジで入ったことがわかっており、静かに相手に歩み寄り握手を求めたのだった。
どんなことをしても勝ちたい勝負がかかった場面でのこのような行動こそが讃えられるべきなのだ。ほとんどの選手はこんなことはできないだろう。しかし、だからこそ人を感動させるしいつまでも讃えられるのだ。
そのわりに名前を忘れたが。