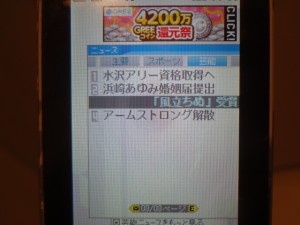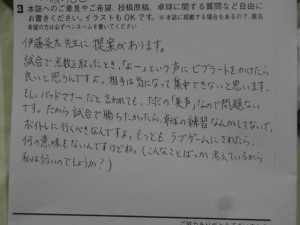読者からスーザン・ボイルが歌ったのはオペラではなくてミュージカルとのご指摘をいただきました。たしかにそうでした。ここに訂正をさせていただきます。
偽作曲家騒動
別人が作曲をしていたという騒動が世間を賑わせている。
この騒動を通して私が思ったことは、クラシックという音楽の置かれた状況についてだ。それは、今やクラシックは、音楽そのものの魅力だけではなくて、その他の物語がなくては売れない物であるということだ。確かに、今まで佐村河内氏の音楽がよいと思って感動をしていた人たちは裏切られたと思っているだろう。しかしそれはもちろん、音楽のクオリティそのものにはなんら関係のないことである。今回の事件で佐村河内氏の「音楽」に対する評価が変わった人は、結局、音楽の良し悪しがわかって聴いていたわけではないということなのだ。
そうでないのなら「作品そのものにはなんら罪はない。経緯はどうあれ、新垣氏の生み出した音楽の魅力は永遠に輝き続ける。自分はあの楽曲群をずっと聴き続ける」とでもいう論陣を張る者が出てこなくてはおかしい。
クラシックとは、ごく一部の鑑賞能力のある人にしかわからず、その他大勢の人たちは彼らの評価をうのみにするかまたは付随する物語やステイタスによってしかその音楽性を評価できない「芸術」だということなのだ。
オペラについても似たようなことがいえる。スター番組で一夜にして有名になったスーザン・ボイル、ポール・ポッツといった人たちが歌ったのがポップスではなかったことは偶然ではない。オペラならポップスと違って外見の影響を受けずに歌唱力だけで評価をされるからだろうか。それだけではない。オペラは、現代ではそれほどポピュラーではないために、一定以上の歌唱力があればその良し悪しは大衆にはわからない音楽だから「一夜にして無名からスターダムになった」という感動的な物語が効率よく作用したのだ。確かに私もスーザンとポールの声は良いと思う。しかし、その他のオペラ歌手より特別良いかどうかはまったくわからない。聴いたことがないし、聞いてもわからないだろう。
こういうことがあるのは音楽だけではない。味だけではなく、その値段やステイタスで選択されることが多いワイン、酒、高級料理もそうだ。わかる人が少ないからこそ利き酒大会があり、芸能人が高いものと安いものを判別できるかどうかの番組も成り立つ。本当に味だけで価値を判断される大衆料理やジャンクフードではそれらは成り立たないし「専門家」の意見がどうあれ、誰でも自分が好きなものを選ぶだろう。「天然物を使っているこのカップラーメンこそ本当に旨いのだ」という専門家の意見は、最初に買うときこそ参考にしたとしても、食べてみて旨くなければ二度と買うことはない。これらは味だけで自分で判断するべきものと認識されているからだ。
世の中に値段が高くておいしいものは数あるが、それらのなかで「高い」「貴重だ」という付加価値を外してなお、ラーメンやソース焼きそば、カレーライス、餃子と戦える料理がどれだけあるだろうか。私にはそのような料理はとうてい思いつかない。こんなに旨いものを安く食べられる我々はなんと幸せなのだろうか。
いやすっかり話がそれたが、物事の価値というものについて、そんなことをあらためて思い起こさせられた偽作曲家事件であった。
同様の考察をラケットやラバーについてもしてみると面白そうだが、ちょっと怖くもあるから止めておこう。
アームストロング、解散!
立体駐車場メーカーの人
先日、出張でまた天王洲の東横インに泊まったのだが、ファイナルの編集も終わったので、久しぶりに近くの小さな居酒屋に入った。カウンターしかない、6人ぐらいしか入れない店だ。私はこういう店にひとりで入るのが楽しいのだ。新しく届いた卓球王国を読もうと持って入ったのだが、入って間もなく、隣のサラリーマンに話しかけられ、結局、雑誌を読む時間はなかった。
仙台から来たというと、偶然にもその人は1年半、仙台支店にいたことがあるそうだ。なんでも、立体駐車場メーカーのセールスマンをやっているとのことだ。そういう職業の人とは初めて会ったが、立体駐車場メーカーは主要なものは日本に11社しかないそうで、どうりで会ったことがないわけだ。
その人は藪から棒に「仙台では焼きそばの上に麻婆豆腐を載せますか」と言う。そんなのは見たことも聞いたこともないと言うと、テレビ番組で言っていたそうで、仙台支店に赴任したとき、誰に聞いても知っている人はいなかったそうだ。それで、いまだにそれが納得がいかず、仙台の人に会ったら必ず聞くのだという。ひどいテレビ番組もあったものだ。ところがその人は先日、焼きそばの上に麻婆豆腐を載せて食べてみたら「これが旨いんです」と言う。旨いかもしれないが塩分をとりすぎではないだろうか。
立体駐車場メーカーならではの薀蓄も聞いた。立体駐車場は、売るだけではなくて、エレベーターと同じようにその後の点検や整備をすることでも利益を得るのだそうだ。ところが最近はなぜか立体駐車場を止めてしまうオーナーが多く、あまり景気がよくないという。都心で重宝しているのは、墓地の立体駐車場だと言う。建物や設備を作るときにはその大きさに対応した駐車場を必ず設置しないといけない「附置義務」というのがあり、土地が狭い都心では立体駐車場のニーズが高いのだという。
他にもいろいろと話を聞いたが、何しろ酔っていたので忘れた。
読者からの提案
四元豚
先日、駅の食堂に入ったのだが、例によってメニューを考察したくなった。
「牛たんシチューをのせて」とは、なんか「私をスキーに連れてって」風な名前だ。あるいはこれはお願いではなくて「のせて、美味しかった」などと続く文章の途中なのだろうか。いずれにしても、名詞ではない文章のメニュー名になっているところが新鮮だ。
「市場から仕入れた」とわざわざ書いてあるということは、このクジラベーコン以外はすべて食品卸業者から買っているかまたはスーパーで買っているということなのだろう。ううむ。
「四元豚」って、「よつもとぶた」って読むんじゃないよな、と思って調べたら「よんげんとん」で、4種類の豚をかけあわせた品種だということだ(ホッとした)。他に三元豚(さんげんとん)というのもあるらしい。
編集の跡
昨年に続いて『ザ・ファイナル2014』の編集の様子を紹介しよう。
プロダクションから送られてきた素材の映像が入ったDVDは全部で23枚。それぞれに4〜5時間の映像が入っている。その合計時間は、昨年より20時間多い約100時間だった。
手書きのメモを見ながら、それらの映像を順番にチェックしていく。当然、見るのはラリーの部分だけで、それ以外のところはグングン早送りしながら見るので、実際の時間の半分以下で終わる。とはいえ、ラリー部分は実速で見るしかないので、やはり時間はかかる。見ながら「これは」と思うラリーを編集ソフトでどんどん抜き出して行く。二度とやらなくてよいように、ラリーは多めに選ぶことになる。
そうしてすべての素材を見終わって選んだラリーの合計時間は、今回は150分だった。あとはここから半分に絞って、ああでもないこうでもないと入れ替えたりして90分の作品にする作業だ。これが実に楽しい。なにしろすでに選んだ良いラリーばかりなのだから、嬉しくて自然と笑みがこぼれる。度を越したスーパープレーには興奮し、深夜の高笑いをすることになる。ラリーに興奮すると笑いが出るのは考えてみると不思議だが、友人の田村も、いつも鬼気迫る目つきで大笑いをするので、これは誰でもそうなのだろう。
目、肩、腰と、体は疲れるがなんとも楽しい4週間であった。
ザ・ファイナル2014完成!
やっと全日本のダイジェストDVD『ザ・ファイナル2014.1』の編集が終わった。あとはDVDをプレスしてもらうのを待つのみとなった。この4週間というもの、家でも移動中でもとにかく本業の仕事と寝る時間以外はずっと編集をしていた(今野さんとの電話雑談を除く)。
長すぎる作品はよくないと思っていたのだが、あまりにプレーが素晴らしいのでカットできず、結局昨年より20分長い100分になってしまった。画質も向上する策を施した。選手紹介とともにラリーを紹介したのは全部で78試合。その他に選手紹介のないスーパープレー集やら珍プレー集がある。
ウエブ用に画質を落としたサンプル映像がアップされているのでぜひご覧いただきたい。
https://world-tt.com/ps_movie/movie_member.php?selMovNum=217
メダル噛み
オリンピックのメダルを噛むなとか選手の勝手だとか論争になっていると聞く。「噛むな」と言う人は、メダルを冒涜することになるとか品がないとか言っているようだ。
まずはっきりさせたいことは、あれは本人が噛みたいのではなく、カメラマンが噛んでほしいとリクエストをしているのだということだ。メダルを口に入れて歯を当てたい人など、特殊な趣向の人を除いているわけもない。となると、あとはその選手がメダルを獲得をした嬉しさで気前がよくなりカメラマンのリクエストに応えるのか、それとも断るのかという問題になる。
私は冒涜だとも品がないとも思わないが、別の理由でぜひとも断ってほしいと思う。理由は、もともと「純金であることを歯形がつくことで確認する(金は柔らかいため)」という、本来は意味のあった行為を、形だけの無意味なものにして得意になっている様子(なにしろ笑っているのでそう見える)を見るのが嫌だからだ。
しかしまあ、それはカメラマンのセンスと選手の許容力と批判能力の問題なので仕方がない。そういう人たちなのだと思って諦めるしかないだろう。
松田聖子の歌
学生時代からずっと主張していて、誰の賛同も得られたことのない説を披露しよう。
松田聖子の「Rock’n Rouge」という歌がある。
若い男女の恋愛についての歌なのだが、その中に「キスは嫌と言っても反対の意味よ」というフレーズがある。言葉にこだわる私としては、この歌詞がどうにもひっかかるのだ。もちろん作者の意図はわかる。恥じらっている女性が本当はキスをしたいのにそれが言えず「嫌よ」と反対のことを言っているという状況だろう。それはわかる。
しかし私には「反対の意味よ」というところが、言っていること自体が反対なのではなくて、その背景や理由が反対だと言っているように聞こえるのだ。つまりこうだ。「キスは嫌よ」という言葉自体は本心だ。しかし、その意味するところは、通常ならば「まだそこまで進みたくない」というものだろう。それが反対だということはすなわち「キスなどというヌルいことをしてはいられない、すっ飛ばしてその先に行きたい」と言っているように聞こえるのだ(そんなバカな歌があるかどうかは別にしてだ)。
もしこの歌詞が「キスは嫌と言うのは嘘よ」とか「キスは嫌と言うのは本心じゃないの」とでもいうものなら誤解の余地はなかっただろう。しかし「反対の意味よ」というフレーズがなんとも意味深で、誤解の余地を残すものになっていると私は思うのだ。
私は松田聖子のファンではなくレコードもCDも持ってはいなかったが、カラオケなどに言って誰かがこの曲を歌うたびに、酔った頭で「おっほほ、反対の意味か。それはそれは」などと思っていたものだった。しかしこの説は誰に言っても賛同されたことはなく「どうかしている」と言われるばかりであった。より多くの人に自説を披露する場を得た今、賛同者が少しでも増えないものかと期待している。
また書いてしまいました。大橋先生、ごめんなさい。