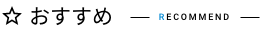兵庫県尼崎市にある「ピンポンバーDANDY(ダンディー)」。2003年のオープンから今年の6月で18年が経った。この卓球場のオーナーであり、コーチとして指導にあたる中村博文が卓球を始めたのは中学生の時であったが、そのキッカケ、そして卓球場を開いた理由は実にシンプルで単純明快。中村の生き様には不思議と人を惹き付ける魅力がある。酒と指導と男と女、中村の卓球人生をご覧あれ。
写真:小寺敬太(関西卓球情報誌TAMA)
「初恋の人が卓球部に入った」。小学校では野球チームで4番・ピッチャーだった中村少年が中学校で卓球部を選んだのは、そんな理由だった。だが、卓球部は同学年だけで36人もいた。そんな中で、使える卓球台は男女で3台ずつ。先輩が優先的に練習するため、1年生はなかなかボールを打たせてもらえず、山に走りに行く日々が続いた。
「練習せな、女の子にモテへん」。そう思って体育館のドアの鍵を壊して忍び込み、同級生と朝に練習するようになる。その甲斐あって大会でも成績を残せるようになると、会場で他校の女子生徒からファンレターをもらうようになり、「これはええわ。強くなるっておもろいな」と思った。「強くなる=モテる」という素直すぎるモチベーションで練習に精を出し、どんどん卓球にのめり込んでいく。
高校時代には兵庫県大会でベスト8に勝ち進む。インターハイ出場はならなかったが近畿大会に出場し、後に世界選手権3位となる高島規郎と対戦した。1、2ゲームとも中村が18-17でリードし(当時は21点制の3ゲームズマッチ)、「よくわからんやつが高島をやっつけとる」と会場の注目を集めたが、そこから高島はまったくカットをせず、攻撃に転じて逆転。結局、1ゲームも奪えずに敗れた。「あそこで勝ってたらもう少し有名になれたな」と中村は高校時代を笑いながら懐かしむ。ちなみに、卓球を始めるキッカケになった「初恋の人」とは高校時代に付き合ったが、1、2年ほどで別れたそうだ。
高校卒業後は企業に就職。全日本実業団ではベスト16まで勝ち上がったが、「会社に練習相手がいない」という理由で2年で退職し、大学に入学して部活で卓球に取り組むことに決めた。だが、当時は社会人の大会で実績がある選手が大学に入学した場合、1年間試合に出場できない規定があり、中村は実力をアピールする機会がなかった。
また、先輩との関係も良好とは言えなかった。大学1年生でも年齢は大学3年と同じ中村にとって、大学2年の先輩は学年では上でも、年齢では下になる。しかし、そこは体育会であり、年功序列の世界。同年齢の3年生と親しげにしていると、2年生からいちゃもんをつけられる。それに耐えきれず、「もうアカン」と喧嘩の末に卓球部を辞めると大学も辞めた。
大学を辞めると、クラブのボーイとして働き出した。大阪・キタを代表する歓楽街・北新地でも5本の指に入るような高級クラブだった。
「その頃、一般的な時給が250円くらい。でも、北新地は350円で100円も高い。ほんで行ってみたらキレイな人がぎょうさんおる。全員で100人くらいおったかな。ボーイの仕事は1年かそこらやったかな。北新地ではいろいろ勉強させてもろたな」
その後は知り合いの伝手で日本生命に就職。営業として、朝から晩まで働く毎日を送る。夜には接待もあり、翌朝は二日酔いで出社し、夕方になって酔いが醒めてきた頃にまた飲みに行く、なんてこともザラだった。ただ、接待の席などでも北新地でのボーイの経験は活きた。
「知り合いもぎょうさんおるから、飲みに行ったら安くしてくれることも多かった。北新地ではいろいろ勉強させてもろたね」
大学を退学した後は卓球からは離れていたが、日本生命に卓球部があることを知って入部。本人曰く「練習して飲みに行くために卓球をしてた」とのことだが、全日本実業団などに出場。その後、女子部が日本リーグに加盟する前後の時期までコーチ、監督も務めたが転勤となり退任。頻度は減ったが転勤後も卓球は続けており、縁あって武庫川女子大のコーチも務めるなど、卓球を教えることもあった。
ツイート