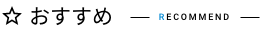<卓球王国2003年10月号より>
【ピンポン外交50周年】
中国
Vol.4 Chuang Tsetung

伝説のチャンピオン、波瀾万丈の人生を語る
[逆境が人を諫める。栄誉と恥辱に動じない]
1971年世界選手権名古屋大会。
バスに迷い込んだひとりのアメリカ選手に声をかけたことで、
荘則棟は一躍ピンポン外交の主役となった。
その後、74年にスポーツ大臣までのぼりつめた荘則棟は
76年に四人組逮捕とともに失脚し、投獄された。
世界チャンピオンとスポーツ大臣。ふたつの栄光をつかんだ男はどん底に落ちていった。
インタビュー・写真 ● 今野 昇
通訳 ● 杜功楷
1966年に始まった中国の文化大革命という政治運動のために、中国卓球チームは67年と69年の世界選手権の参加を取りやめた。文化大革命は依然続いていたものの、71年に日本の名古屋で開催された第31回世界選手権大会に6年ぶりに姿を見せた中国チーム。
その大会で、偶然にも荘則棟とアメリカのコーワン選手との交流が始まり、これが直接のきっかけとなり、アメリカ卓球代表団の訪中、ニクソン大統領の訪中、中国卓球代表団の訪米、そして79年の中国とアメリカの国交樹立というように、ピンポン球は国際政治、歴史の舞台のラリーを作っていった。
◇◇◇◇◇◇◇◇
71年の世界選手権名古屋大会がきっかけとなって、中国とアメリカの「ピンポン外交」が始まりました。大会後に、アメリカ選手団が中国を訪問した際に彼らは中国のスポーツ界と中国人民に熱烈に歓迎されて、周恩来総理も直接アメリカチームと接見しました。その頃、中国卓球チームはまだ日本に残り、各地で交流会を行い、我々が中国に戻ったのは6月でした。
7月に人民大会堂で会議があった時に、我々卓球チームも出席し、一番後ろの席に座っていました。すると周恩来総理が突然、中米外交の話に触れ、「中国卓球チームの人たちはここに来ていますか。どこにいますか。荘則棟は来ていますか」と言い出しました。
周恩来総理はその時、「みんなで拍手して、中国卓球チームを一番前の席に迎えましょう」と呼びかけました。何千人もの万雷の拍手の中、我々卓球チームは一番前の席に向かいました。そして総理に「今回アメリカチームが中国を訪問しましたが、来年、アメリカから中国チームを招待したいという話があります。あなたたちは行く勇気はありますか」と聞かれたので、「私たちは行きます」と答えました。
国家体育委員会の幹部たちは訪米チーム代表団の団長や副団長になりたがっていましたが、周恩来総理は「荘則棟が団長になってチームを連れて行ってください」と言いました。
72年2月にニクソン大統領が訪中し、人民大会堂で開かれた歓迎パーティーで、周恩来総理がニクソン大統領と一緒に私の前に来た時に、「この人が一番最初にアメリカチームの人と友だちになった荘則棟です」と大統領に紹介してくれました。大統領はとても喜び、「あなたがアメリカを訪問する時は私がワシントンに招待します」と言ってくれました。
これが「ピンポン外交」の話ですが、私、荘則棟はボールを卓球台のこちらから向こう側に打つだけの選手です。私は卓球しかできない。時々はネットするし、時々はオーバーもします。
ところが、この「ピンポン外交」では、地球の上で、ピンポン球を中国からアメリカに打ちました。中国には毛沢東、周恩来がいて、向こう側にはニクソンとキッシンジャーがいた。お互いが海を越えてピンポン球を外交というラリーで打ち合ったのです。
アメリカ人にとっても中国との冷戦の終結というのは「ピンポン外交」の時ではなかったかと思います。中米の冷戦はこの「ピンポン外交」で終わり、東西の緩和はここから始まったとするならば、これは人類の平和に歴史的な貢献をしているのではないでしょうか。
もしバスの中で私がコーワンに話しかけなかったら、中米の友好の始まりはもう少し遅れたかもしれませんね。ただ、当時、毛沢東主席もニクソン大統領も本当は中米の友好を望んでいたのですが、きっかけがなかっただけです。また、この「ピンポン外交」はその後、72年の日本の田中角栄首相の訪中、日中国交回復にもつながりました。
日本にとって、アメリカと中国が友好的になるということは、日本の空を飛び越えた外交であり、日本には挨拶もしなかった飛び越え外交だったわけですが、日本のほうが中国に近いから先に国交をスタートしたわけです。これも「ピンポン外交」のひとつの歴史的な結実と言えるでしょう。
ツイート