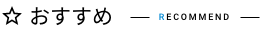藤本 賢司
[明豊高等学校・中学校 卓球部総監督]
昭和の香りがする気合い満点の丸坊主軍団・明豊中高卓球部。このチームが最初に日本のジュニア卓球界に衝撃を与えたのは、今から19年前のことだ。
2003年の全日本カデット(14歳以下の部・男子)でベスト4のうち3人を明豊中の選手が占拠。さらにはその勢いで04年春の全国中学選抜、同年夏の全国中学校大会団体を相次いで制覇したのだ。
全国的には無名に近かった地元大分の子どもたちを一躍日本一にしたのが、自他ともに認める鬼監督・藤本賢司だった。
「あの時は甲斐(義和)、江藤(遼)とか良い素材がいたから、最初から日本をとるつもりでやっちょった。みんな通学生だったから、ぼくが別府駅に朝7時ごろ迎えに行って、その子らの授業のカバンとか全部車に積み込んで、子どもらには約2km上り坂を走らせて学校にやり、それからすぐ朝練。終業後は夕方4時ごろから夜の9時、10時まで健勝苑(以前あったSC卓球場)で練習。それを毎日です」
当時はまだ学校の体育館が使えず、校内の特別棟や野球部の寮の一角など、練習場所をあちこち探し回っていた「ジプシー状態」。その中で、今では御法度の鉄拳制裁も交えての猛特訓を課し、さらには会社経営で蓄えた私財を投入しての韓国・中国遠征も敢行。まさに執念と言える指導で最強軍団を作り上げた。
「よう耐えたわ、あの子たち。でも、そんだけ練習やると、子どもたちの中に自信がつくんですよ。その頃の王者・青森山田なんかとやる時も『全然大丈夫です、勝てます』って言うくらいだった」

2004年の全国中学校大会を制した明豊中。鍛え込まれたフィジカルと闘争心で他チームを圧倒した
とにかく修羅のごとき勝負師、というイメージが先行する藤本だが、いったいこれまでどのような卓球人生を歩んできたのだろうか。聞いてみると、卓球と出合ったきっかけは、本当にひょんなことだった。
「うちの実家の前の雑貨屋の“おいちゃん”が卓球大好きで。いつも自分の店のガラス戸に向かって素振りしてたんですよ。で、そのおいちゃんに『それ何?』って聞いたら、『卓球』っちゅうんです。『賢ちゃんも一緒に行くかい?』って言うから、『いいよ』って言って。それが最初。小学校3、4年生の頃です」
そして、中学1年の時にはさらに運命的な巡り合わせが訪れた。1巡目大分国体の会場が、たまたま藤本の通う日出(ひじ)中学校の体育館となり、藤本はその大会の手伝いをしながら全国トップクラスの卓球を初めて生で目の当たりにしたのだ。
「卓球すげえな、と。その時は卓球部と陸上部の2つに所属してたんですけど、最終的にはそれ(国体)を見て『俺は卓球にしよう』と決めました」
その時の大分県の少年男子の代表は大分商業高(通称・大商=だいしょう)。ぼくもあの高校でやりたい、と件の雑貨屋のおいちゃんに言ったら、おいちゃんも大商OBだったこともあり、「そら賢ちゃんいい。やりなさい」と背中を押してくれた。
かくして本格的な競技人生のスタートを切った藤本だったが、その幕開けはなかなか厳しいものだった。
「高校入ってすぐ、ぼくが学校に下駄履いて行ったら、卓球部の先輩4人くらいから『お前卓球部に入るんだったらそんな格好してくんな』って言われて袋叩きでボッコボコにされました。ふつうはそんな格好してたら学校の先輩含め誰も近寄って来ないんだけど、卓球部だけは違った。『ああ、ここは怖いところだ。ちゃんとやらんといかんな』って思いましたね」
中学までやんちゃ放題だった藤本少年をも慄然とさせるほどの厳しさだった大商卓球部。それでも、その中で着実に力をつけた藤本は高校3年時の国体大分県予選で堂々の1位となった。しかし――
「1個下に全日本ジュニアで3位か2位になった後藤(専修大→信号器材)っていうのがいて、戦型がぼくと同じペン表だった。チーム戦略として表2枚は要らないというので、ぼくが落とされたんです」
当初は高校で卓球を辞めようと思っていたという藤本だったが、そこで「むかっ腹が立った」と、生来の反骨心に火がついた。その一件を境に大学志向となり、受験には無縁に近い商業高校というハンデを負いながらも勉強を開始。同郷の先輩を頼って國學院大に進学した。
「どうせ行くなら『関東を制する者は日本と世界をも制する』っちゅう言葉もまだ生きていたので、関東だと。ただ関東の一番は自分でも自信がなかったから5、6番目だった國學院を選びました」

藤本の子どもたちに対する厳格な指導は、自らが高校・大学で厳しい環境を耐え抜いてきた経験がバックボーンになっている。「やらされるんじゃなくて、自分からそういう世界に飛び込んでいく気概が大事だと思うんです」
國學院大も大商に負けず劣らず、厳しい環境だったという。東京選手権のダブルスで優勝したり、世界選手権の代表選手を倒したりするような先輩もいて、かなりレベルは高かった。藤本はそんなチームで1年時からレギュラーを張ったのだが、そこにはこんな裏話がある。
「酒飲みの席で、ある先輩が『俺のゲ●飲んだらお前は即レギュラーに入れてやる』と言ってきたので、飲んだ。それで、次の日に『ぼくレギュラーですよね?』って言ったら、その先輩が『知らねえ』つったから、『お前!』って言って飛びかかって大暴れして。そこからずーっとレギュラーだった」
……現代ではとても考えられない、昭和の時代でもかなり珍しい部類の話だが、藤本の豪傑ぶりが十分に伝わるエピソードと言えよう。
それから、東京で4年を過ごした藤本はすぐに帰郷し、別府溝部学園高に教員として赴任。学校になかった卓球部をイチから作って奮闘したが、「その頃はまだ若かったし、自分に自信がなかった」こともあり、5年ほどで教壇を降りた。
「その後、会社を作ったんです。建築設計と行政書士の事務所から始まって、コンピューターやテレビ、ファクシミリを扱う業務、下着の販売なんかもやりましたね。その時はバブルもあって、よう儲かりました」
しばらくは卓球と無縁の生活をしていた藤本だったが、会社の儲けをただ税金で持って行かれるよりは福利厚生に回そう、ということで、実業団的な会社の卓球チーム「フジヤマ」を作った。ネーミングには、どうせやるなら日本一を目指す、という意気込みを込めた。
「その頃、大分県は九州で一番弱かったと思うんですよ。国体なんか行っても、大分に当たったらラッキーってみんなから思われていたので、とにかく弱い大分に気合いを入れようっていう思いだった」
ほどなくして、フジヤマジュニアという子どものクラブも立ち上げた。藤本は軸足をジュニア育成に移し、会社からもらう役員報酬のほとんどをそこにつぎ込んだ。
そうこうしているうち、2008年に2巡目大分国体を控えた地元では、強化の拠点校を作ろうという動きが本格化。明豊中高がその受け皿となることが決まり、指導者として推挙されたのが、ほかならぬ藤本だった。
「(その話を受けるかどうか)迷ったんですよね。仕事もあったし、50歳くらいから学校に入ってまた、そういう生活ができるのかどうか、とか。まあでも、自分自身も卓球で育てられたっちゅう思いがあったので、恩返ししようかなということで決意しました」
かくして藤本は、自らが育てたフジヤマジュニアの愛弟子たちを引き連れ、2002年に明豊中卓球部の監督に就任。そして冒頭の通り、2年後には破竹の勢いで全中制覇に成功したのだ。ここで藤本の野望、フジヤマ=日本一は、現実のものとなった。

2008年2巡目大分国体、藤本は地元・大分県少年男子チームの指揮を執り、明豊中高の混成メンバーで県勢過去最高成績の2位を勝ち取った。成年男子も藤本の教え子たちが活躍し、5位入賞を果たした(画像は卓球王国2008年12月号の国体報道ページ)
明豊中高の指導を始めて約20年。今春に古希を迎えた藤本は「以前の100分の1くらいにやさしくなった」(女子部監督・松本香織氏談)とも言われるが、基本的な「叱る」スタイル、徹底的な厳しさは、ブレずに変わっていない。
「当たり前のことを当たり前にしない。人として違うことをする。具体的に言うと、試合や練習でキレる、あきらめる――そういう時、ぼくは怖いですよ。ヘボなやつらは相手の学校名や選手名で『勝てない』と決めつけるけど、そいつに簡単にあきらめて負けて帰ってきたら俺は許さんぞ、っち。極端に言えば、相手が怖いのか?俺が怖いのか?ちゅうことですよね。そしたら、結構勝つんです(笑)」
ぼくの指導の中心は、意識改革です。意識を変えないと、やっぱり強くなれない――そう言い切る藤本。やり方の是非はともかく、そこには確固たる信念と強烈な反骨精神があるのだ。
「強いところを倒したい。全国トップの強豪校はホープスとかカデットとか全中とかのチャンピオンがオーダーにズラッと並んでいるけど、こいつらを倒さないかん。それを無名の選手が頑張って、2年半や5年半で勝負をかける。そらお前たち、髪いじったり携帯いじったりする暇ねえぞって(笑)」
男子は全員丸坊主。携帯電話の所持は中高6年間禁止。鉄の掟とも呼ぶべき明豊中高卓球部の約束事=藤本のポリシーの裏には、勝負に対する徹底的なこだわりがある。選手たちも藤本を信じ、それを愚直に守って黙々と練習に励んでいる。
それだけに、昨今のコロナ禍におけるプレーや応援の各種規制には、かなり頭に来ているという。
「もう最悪ですね。その最たるものがインターハイ。選手に大声出すなと。大声出して、ひどかったらイエロー出て、最終的にはレッドを出して相手に点数をやるって。観客席、もしくはベンチで立ち上がって応援すると退場……そんな、選手ファーストじゃないような文言が監督会議の中で出されたので、ちょっと待てよと」

2022年の愛媛インターハイ。新型コロナ対策の題目のもと、選手たちはプレーや応援における不自由を余儀なくされた。一生に一度の晴れ舞台で全力を出させてもらえない選手たちを、藤本は非常に不憫(ふびん)だと嘆く
今夏の愛媛インターハイ、監督会議の席上で藤本は運営側に噛みついた。子どもにばかり我慢を強いて、大人が責任逃れをしている――そう思えて仕方がなかったのだ。
「感染防止ってのはわかるんだけど、もっと違う手はないのかと。もっと頭を使って腹をくくれと。たとえば各チームが自費で抗原検査キットを用意して、毎日それをやって、陰性の子だけを会場に入れたらあとは力一杯やらせてくれ、っちゅうのがぼくの思いなんですね」
下剋上を狙う雑草軍団ならではの忸怩(じくじ)たる思いもある。
「うちのチームは練習の時からね、ベンチと選手と観客席にいる応援とが一体になれって教えるんですよ。そういう思いになって戦わないと、君たちヘボなんだから勝てないよと言うんだけど、それができない。かわいそうだと思う、コイツら。
だから、次の選抜までに変わらんかったら、俺はまた1時間でも2時間でもマイクとって攻撃……攻撃じゃないな(苦笑)。主張するぞっていう風に言ったんです」
口は悪いが、腹の中にあるのは選手たちを大事に思う気持ち。コロナ対策は一筋縄ではいかない問題だが、藤本の言い分も大いに理解できる。何とか少しずつでも、改善に向かうことを願いたい。
ところで、藤本は何も卓球で勝つことばかりを子どもたちに教えているわけではない。一番大事にしているのは人間教育。鬼指導や勝負へのこだわりは、その一手段なのだ。
「卓球自体は、そこそこでもいいと思う。その先をどう生きるか。そっちが大事。それは自分が会社作って仕事してきて、つくづく感じたこと。だから、ぼくはコイツら(選手たち)と毎日、いっつも本気で張り合ってますね」

かつての鉄拳は封印し、今は選手全員のノートにメッセージを書き入れるのが藤本の日課。選手が負けた時には「○月×日のノートを見ろ、そこに答えが書いてある」といったアドバイスをして、驚かれることもしばしばだという
ほぼ1年365日、寮監として子どもたちの生活指導も行う藤本。やんちゃな我が子を矯正してほしいという思いで親から預けられる子も少なくないため、毎日が格闘なのだという。
「モノは壊す、ごみの出し方は知らん……こんなんが世の中出ていったら大変、と思って怒りまくりです(笑)。でも、手のつけられんクソガキが、最終的にふつうの子になってくれた時や、そういう子が全国のトップで互角に戦えるようになった時は、最高ですね」
「かつてクソガキだった俺」だからこそできる卓球指導と人間教育。藤本はこれからも、それを貫いていくだろう。
※ PEOPLE 藤本賢司 は「卓球王国2022年11月号」でも掲載しています。
ツイート