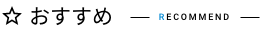<卓球王国2007年3月号より>
Penholder Never Dies.

全日本選手権で2連勝している中国式のペン裏ソフトドライブ型、吉田海偉
指導者に「ペンホルダーでも大成できる」という意識がないと、実際に指導する時にもペンホルダーを教えられない。
日本卓球協会のマリオ・アミズィッチコーチがセミナーの時に印象に残る話をしてくれたことがある。「○○スタイルだから勝ちやすい、○○式だから強い、というのはない。今はシェーク攻撃が強いかもしれないけど、いつの日かカット全盛の時代が来るかもしれないし、ペンホルダー全盛の時が来るかもしれない」と。
ペンホルダー選手を育成していく条件として二つ挙げるとすると、第一にペンホルダーでもやれるという意識を、選手・指導者が持つこと。第二にどのようなプレースタイルを目指すのか、ということ。
特に男子のペンホルダー攻撃型の選手は、身体能力の高い人でないと大成しないと私は思う。ペンホルダーの特徴を生かすために、フォアハンドで動くプレースタイルになるので、どうしても体力的要素が重要になる。よって、指導者も選手の総合的な能力を早い段階で見極め、プレースタイルを決めていくことが肝要である。
平成13年度より、日本卓球協会の競技者育成委員会において、全日本選手権大会ホープス・カブの部からセレクトした小学生を対象に研修合宿を行っているが、身体能力が伸びていきそうな選手は多い。この段階で、小学5、6年生は卓球をすでに3、4年はやっている。
そのプレーぶりを見ていると、持って生まれたハンドフィーリング(手の感覚)や、その子の持つ資質、特性を見ることができる。また、体操やランニング、そして、簡単な体力テストなどを実施しているが、卓球に向いたアジリティー(敏捷性)を発見することもある。
1970年代に日本代表として活躍した井上哲夫さん(77年世界選手権団体2位のメンバー)は、ペンホルダー表ソフト攻守型の選手であった。井上さんは手の反応と動きが抜群に速く、その点を評価されていた。もし井上さんが、時の世界チャンピオンであった長谷川信彦さんのようなシェークハンドドライブ選手になれと言われても難しかったであろう。その選手の持って生まれた長所・才能を生かしながらプレースタイルを決めることが大切であり、指導者の眼力と、指導力で選手の成長が決まっていくと言っても過言ではない。
今、子どもたちを指導されている指導者の多くは、ペンホルダーラケットを握っていた人ではないか? それなのにペンホルダーではなくシェークハンドの選手を多く育成するという最大の理由は、背が小さいとペンは不利、シェークハンドのほうが勝ちやすいということ。つまり、早い時期から勝たせたい、という考えと、勝てないと子どもたちが嫌になってしまうということがあるのであろう。ここまでシェークが増えてくると、「ペンホルダーでも勝てるんだ」というプロパガンダがないと指導者がその気にならないのかもしれない。ペンホルダーでもサービスがうまいとか、一発で仕留める決定打があるといった特長のあるプレースタイルなら勝てるという雰囲気を漂わせることが必要だ。
現に、04年アテネオリンピックの決勝戦は柳承敏対王皓、06年世界選手権ブレーメン大会優勝の中国男子チームには馬琳がいた。06年アジア競技大会の男子ベスト4は、王皓、馬琳、柳承敏、李静のペンホルダー選手4名であった。また、日本国内でも全日本男女チャンピオンは吉田海偉、金沢咲希両選手である。ペンホルダー選手が国内外ともに活躍しているのである。

柳承敏vs.王皓。2004年アテネ五輪の男子シングルス決勝は、ペンホルダー対決となった。ペン裏ソフトドライブ型の柳承敏(韓国・手前)とペン両面ドライブ型の王皓(中国)の対戦。柳承敏が勝利し、金メダルを獲得した
ツイート