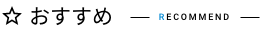4月9日、10日に行われたアジア競技大会の日本代表選考会。4人ずつ(1名棄権)のリーグ戦の1位同士が対戦し、優勝した選手がアジア競技大会のシングルスの代表枠を獲得できる。
卓球にはアジア競技大会とアジア選手権があり、4年に一度のアジア競技大会は「アジアオリンピック」と言われ、各国のNOC(オリンピック委員会)が選手を派遣する。JOC(日本オリンピック委員会)としては五輪に次ぐ大会となる。
一方、アジア選手権大会は2年に一度、ATTU(アジア卓球連合)が主催する大会だったが、今ではITTF(国際卓球連盟)傘下の大会となっている。
オリンピック方式のため、シングルス枠は各国(協会)に2名分しかない。
今回、その数少ないシングルス枠を吉村真晴(愛知ダイハツ)が獲得した。決勝では野田学園の後輩であり、全日本チャンピオンの戸上隼輔(明治大)を破り、優勝を飾った。
「気持ち的にはチャレンジャーでしたね。彼は全日本も優勝しているし、最近活躍しているし、ちょっと『お手合わせ』お願いします(笑)と。最近の若い選手はレシーブから一撃で仕留めるようなチキータを持っているし、試合中ずっと怖さを持っていました」とシングルス代表を決めた翌日のインタビューで答えている。
「理想は若い選手のように打球点の高いところで攻めたい気持ちも常にあるけど、高校生の時の『マッハ吉村』もイメージしつつ、ドイツに行って身につけた、相手にやらせてから盛り返すようなプレーも出していきたい。
一時はバックでつないでフォアで回って決めるというやり方だったけど、今はバックハンドを強化している。バックハンドでストレートで一撃で決めにいくとか、全日本からバックハンドを振るようになってからミスをしたとしても、相手がプレッシャーを感じてくれて、バックでつないだ時に相手がミスをしてくれるし、次の自分の攻撃にもつながってきた。攻守のバランスのすごく良い形になっている。それが攻撃の速さになったり、打たれてもバランス良く守れている。今の自分の調子の良さの要因のひとつですね」(吉村)

選考会の決勝で高校の後輩の戸上隼輔を破って優勝し、アジア大会シングルスの代表権を獲得した吉村真晴
吉村真晴のように山あり谷ありの卓球人生を歩んだ男の話は面白い。
最初に「月刊卓球王国」がインタビューしたのは2012年1月に全日本選手権で王者・水谷隼を決勝で逆転で破り、高校3年で優勝した直後だった。「他人と同じセオリーどおりのことをやりたくないし、他の人と違うところを見てほしい部分もあります。自分のそういう考え方は自分でも面白いと思うし、競った場面で思い切ってレシーブしたりとか、思い切ったプレーをするのが好きなんです」(卓球王国2012年4月号)。
当時から型破りのプレーヤーだった。しかし,若きチャンピオンはそこから苦悩の道を歩むことになる。3年間の沈黙を経て、2016年リオ五輪の団体代表に決まった時にこう語っている。
「がむしゃらにやって負けたくない。それで負けたら恥ずかしいと思っていた。チャンピオンとしての無駄なプライドが邪魔をしていた。今考えれば、全日本で与えたイメージが強すぎて、自分のイメージと周りが持っていたイメージのギャップが大きすぎた。
自分自身を過大評価していて、『全日本でのプレーはできるはずだ』と思い込んでいた。でもやってみるとできない。ただ荒々しいだけの卓球になってしまう」(卓球王国2016年2月号)
全日本チャンピオンとしてのプライドに自ら苦しみ、挫折を味わった。その壁を超えて、リオ五輪では団体銀メダリストとなり、2017年世界選手権では石川佳純と組んだ混合ダブルスで優勝を飾った。日本にとっては48年ぶりの世界選手権の金メダルだった。
23歳での五輪メダルと世界選手権の優勝で満足していた吉村。テレビ出演の機会も多くなり、コメントも面白いと好評だった。本人も「プロ卓球選手とテレビでの仕事」を考えていた頃、昨年10月のテレビ出演中にケガをして休養をせざるを得なくなった。
「ケガした時に2カ月(卓球が)できないと言われた。その期間をネガティブにとらえるのではなく、これは次のための準備期間だなととらえて、その間に『自分がどうしたいのか』と話し合った結果、『それならチーム・マハルを作りたいな』となったんです。マッサー、コーチ、そして弟(和弘)も一緒にやろうと、スポンサーであるTRAIL(トレイル)さんに相談したら、「それなら、本気でやっていこうよ」と結論が出て、全面的にバックアップしてもらいました。今まで一人でやってきて、それで東京オリンピックには出られなかったので、一人ではなく、誰かに見てもらう環境を作らないと自分をコントロールするのは難しかった。それに今は時吉(佑一)さんにコーチしてもらっています。12月から話し合いをしながら全日本前から一緒に練習してました。そうしていく中で挑戦していく気持ちが高まり、モチベーションも上がっていきましたね」と吉村は語る。
団体戦ではいつも日本のムードメーカー的な存在だった吉村真晴。ベンチに入れば常にチームメイトを鼓舞するし、団体戦で活躍する姿を見てきた。
「団体戦の時の自分は仕上がりが良いじゃないですか。チーム戦になるとみんなの代表だから変なプレーできないし、結果を出して帰ってこようと戦っていました。今はその状態でふだん練習をしていて試合をしている感じですね」(吉村)。
リオ五輪でも世界選手権でも、そしてTリーグでも団体戦に燃える吉村がいる。「チーム・マハル」というある種の団体戦を経験することで吉村真晴は蘇った。
「今は(立石)イオタさんが環境を整えてくれて、時吉さんがコーチとして卓球を見てくれて、阿部さんがマッサーとして体を見てくれて、(吉村)和弘も同じチームでやっている。一緒にやっているからこそ、その人たちに喜んでもらえるよう頑張りたい。『吉村真晴と一緒にやっていて良かった』と思ってほしい。今までだったら『ここきついな、負けてもしょうがないかな』となっていた時でも、もうひと踏ん張りできる。選考会決勝(戸上戦)の最終ゲームの1−4の時でも何かしら自分で変えて、何かしら食らいついていけばチャンスがあると思えた」。
ツイート