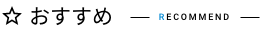2016年、56歳で日本に戻り、早稲田大の博士課程で学ぶと同時に卓球にのめり込む田中敏裕
●ー日本では何をやっていたんですか?
田中 就職する気はなかった。早稲田大の博士課程(大学院アジア太平洋研究科)に入って、人道支援と開発の研究を始めました。それから知的障がい者卓球の強化コーチを頼まれて、パラ卓球の世界選手権大会やアジア大会などに、知的障がい者チームの監督としてヨーロッパや中国・台湾にも遠征しましたね。
ぼくの練習拠点は家の近くの岸田卓球クラブ(神奈川)ですね。56歳で帰ってきてから通うようになって。長崎美柚さんが来られたときに、一度打ってもらったら、ぼくのドライブをバックで倍返しのカウンターされて、今の卓球の違いを思い知らされました。小学生の頃の三木隼くんとか中野琥珀くん(野田学園)と、良きライバルとして切磋琢磨させてもらってました。
チームは東京の九十九クラブに、早稲田大学で同期の高田くんに誘われて入りました。園田監督や河島先輩にマスターズの卓球を学んで。2連覇の時には、東京富士大学卓球部で西村監督にも貴重なご指導いただきました。今がぼくの卓球人生の中で一番楽しく、練習環境や仲間に恵まれて、これから強くなれるんだと思っています。
●ーUNDPの仕事はどう感じていたんですか?
田中 (UNDP/国連は)やりがいのある仕事です。本気で平和を叫んで、困っている人の助けになる仕事ができる。現地の人がとても喜んでくれるのが本当にうれしい。村人とか難民とか、取れた作物を持ってきたり、人と人の生のふれあいが一番大切で、元気をもらえます。ただ、日本でも時々感じるのですが、ぼくは合うつもりでいても、相手がぼくは合わないと思っている人は多いかもしれない(笑)。
●ー学生の時からそういうキャラですか?
田中 変わりようがないですね(笑)。多くの途上国では庶民と特権階級がはっきりわかれています。インドはカーストがあって。人に差があることをそのまま当然のこととして受け入れているけど、ぼくは受け入れられないからね。ぼくが卓球をやっているのは、自分が卓球でより活かされていると感じるからです。組織ではなくて、ひとりの人間として卓球を通じて伝えられることも多い。
国際協力の世界で残念だったことは、スポーツは贅沢品と考えられていて、農業、医療、インフラ整備などと違い、援助分野からとりのこされている。スポーツで人を救おうとは思っていない。スポーツや文化がなかったら人間じゃないでしょ!?
難民キャンプでは衣食住が足りていればそれでよくて。「なぜ音楽?サッカー? 卓球? そんなの必要ない。」と言う人がいる。難民キャンプではスポーツは贅沢なものとして考慮されることもなかった。難民の人たちを人間として扱っていないようで悔しいですよね。オリ・パラで難民選手団が認められるようになったのは、とてもポジティブな出来事でした。
●ーそういう志があったのなら、日本に帰ってきてそういう仕事はすればよかったのでは?
田中 ボランティアでやることはあっても、お金を稼げるような仕事ではないですよ。大学の博士課程に入って、最初は人道支援をテーマにしてミャンマーやフィリピンで現地調査して学会発表とかもしたんです。自分のこれからの人生はスポーツを通じた国際協力だと思ってました。
ぼくはスポーツで、卓球で、みんなの幸福量を増やしたい。それで、障がい者スポーツとインクルージョン(共生社会)が今の研究テーマです。33年前にペルーから帰国する時に「卓球をやっていればまた会える」とペルーの選手たちに約束した。ぼくはこれからの人生は、これまでお世話になった人たちへの恩返しだと思っています。
ツイート