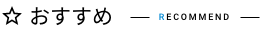福島県南相馬市で開催された日本卓球リーグ・ビッグトーナメント。大会運営の中心人物として会場を東奔西走するのは、一般社団法人日本卓球リーグ実業団連盟の事務局長の小畑幸生だ。試合開始は9時30分。2時間以上も前に会場入りして準備をする小畑は、つかの間の時間をこのインタビューに割いてくれた。(インタビュー・中川学)
―――小畑さんは卓球一家で育ったんですよね。
「はい、父も母も卓球をしていました。父は明治大を卒業後、出身の京都に戻って高校の教員で卓球部の監督をしていたのですが、退職して地元の京都府舞鶴市に卓球場と卓球専門を開きました。
そういう家だったのでぼくも気がついたらラケットを持っていたという感じです。
3歳上の兄と一緒に小学2年から卓球を始めました。
卓球を始めた日から、両親は親から先生という存在に変わりました。練習だけではなく、礼儀などもとても厳しかった。父は家に戻ってからも厳しかったですが、母は家では『お母さん』として接してくれました」
―――その当時(1970年代半ば)はまだ子どものクラブチームは少なかったと思います。
「父のクラブは『一条クラブ』という名前ですが、ぼくが最年少でまわりはお兄さんとお姉さんばかりでしたね。卓球教室はグループレッスンでしたが厳しかったです。『一条クラブはみんな礼儀た正しいね』と言ってもらえることが多かったのですが、そういう部分もとても厳しく教わりました」
―――まだ全日本選手権ホープス・カブ・バンビの部というカテゴリー分けの大会がなかった時代ですね。
「なかったですね。全国ホープスの個人戦には小学5年生で初めて出場しました。ぼくはペン裏ソフトで卓球を始めて、夏の京都予選はペンで優勝して通過したんですが、年末の全国大会にはシェークで出場しているんです。
当時、日本のトップ選手だった前原さん(正浩/現国際卓球連盟副会長、日本卓球協会副会長)が父の大学の後輩ということで、父の卓球場によく来てくれて教えてくれました。前原さんから『これからはシェークの時代だ。変えたほうがいい』と言われて、京都予選後だったけれどすぐにシェークに変えました。でも、ずっとペンでやってきたのでいきなりシェークに変えてもすぐにはうまく打てなくて(笑)。本戦は2回戦で負けました。
翌年に初めて開催された全国ホープス大会の団体戦は、父が監督として京都選抜のメンバーとして出場して、第1回大会で優勝することができました。その時はシェークにもすっかり慣れていて、予選会で優勝してエースとして起用してもらえました。小学生からのライバルで親友の小笠原剛士(東山高でインターハイ個人2位)らと一緒のチームでしたね」
―――シェーク変更がうまくいったんですね。
「はい。前原さんの先見の眼ですね。前原さんと同じように真二さん(佐藤/現日本卓球リーグ専務理事)も父の明治大の後輩として舞鶴によく来てくれていて、小学生のぼくも当時の明治大の練習場の平沼園に毎年練習に行かせてもいました。シェークにしてからは同じシェークの真二さんに憧れて、「目指せ佐藤真二!」バックハンドやフォアーハンドを教えてもらいました。子どもだったのでサーブの出し方やレシーブの構えや仕草も全て真似していましたね(笑)」
―――中学校までは京都で過ごしました。
「中学2年で近畿大会で優勝して全中に出場できました。全日本カデットではベスト8に入ることができて、アジアジュニア選手権の選考会でも代表権を勝ち取り、カデット日本代表として出場しました。大会にはジュニアでキム・ソンヒ(朝鮮民主主義人民共和国)や馬文革(中国)、陳子荷(中国)らが出ていて、強い選手のプレーを間近で見て興奮していましたね。招待試合などを除けば、ぼくにとってはこれが最初で最後の日本代表の舞台でした。ピークが早かったですね(笑)」

日本卓球リーグ・ビッグトーナメント会場にて
ツイート