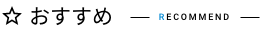1954年ウェンブレー大会で女子チームと荻村伊智朗。右端から田中良子、江口、荻村、渡辺妃生子、後藤英子、後藤鉀二団長、長谷川喜代太郎監督
江口は、大学2年の昭和28年(1953年)11月、奈良県の天理で行われた全日本選手権大会では決勝まで進み、専修大の渡辺妃生子にゲームオール27-29のスコアで敗れ、準優勝。高校時代、全国的に無名だった江口冨士枝は1年間の社会人生活を経て、卓球の名門でもないチーム環境の中で牙を磨き、恐るべき選手に成長していた。
「あの時はお父さんが観に来てくれはったんですわ。大阪からも応援の人も来ていたのに、その人たちの応援の後にひとりパチパチと手を叩いていた」
最初は卓球に反対していた父だったが、いつの間にか冨士枝の最大の応援者になっていた。
女子も男子も代表候補選手でリーグ戦を行い、一人二人と振り落としていく苛酷な選考合宿を経て、江口は1954年の世界選手権ウェンブレー大会の4人の日本代表に入った。
当時の日本卓球協会には資金がなく、世界選手権の日本代表になると負担金の80万円が課せられた。荻村伊智朗のように卓球仲間が街頭募金する選手もいれば、大学のOB会が金を工面するなど、今では考えられないような時代だった。江口は父が負担金を工面してくれたが、お金を工面できなくて代表を辞退した人もいた。当時の貨幣価値は今の10分の1程度とも言われ、今の時代なら800万円相当になる。
日本代表になることは大変な名誉ではあるが、その分、「負けては帰ってこれない」という重圧も並大抵ではなかった。
「今は国際大会や大きな海外での試合も多いけど、昔は世界選手権だけだった。だからこそ、そこへの思い入れや大会の重みが違った」
当時の世界の潮流はヨーロッパのシェークのカットマンだった。男子にはリーチ、バーグマン(イングランド)、シド(ハンガリー)がいて、女子には世界大会6連覇の女王ロゼアヌ(ルーマニア)、ロー姉妹(イングランド)、コチアン(ハンガリー)などの名手がひしめいていた。
大会前の合宿では、男子は貴重なシェークのカットマンだった藤井基男が練習相手を務めていたが、荻村伊智朗、富田芳雄という代表選手は休ませてくれない。藤井が精も根も尽き果て、階段を這うように上っていたのを江口は目撃している。
「卓球界で尊敬する方は多いけれども、荻村さんと藤井さんは卓球だけでなく人間的にも素晴らしかったと思っています」
現役引退後も藤井と親交を深め、卓球の普及の面で江口は荻村をサポートした。
54年当時は羽田空港からプロペラ機に乗り、南回りでイギリスに飛ぶルートだった。タラップのすぐそばまで見送りの人たちが来た。みんなが小さな日の丸の旗を打ち振りながら、口々に「勝ってこいよ、負けて帰るなよ」と声がかかる。
その飛行機で、サイゴン、ベイルート、ローマで給油しながら、終点のロンドン郊外のヒースロー空港に着く。日本からまるまる2日間かかった。飛行機から降りた時に体がフラフラしていたが、直前まで合宿で自分を追い込んでいた江口にとってはそれさえも休養に思えた。
飛行機から降りると、そこには待ち構えていた地元の新聞記者が大勢いた。男子がまず降りて、女子が続いて降りたら、花束をもらい、女子だけ並んで写真を撮られた。
大会の3日前に到着し、翌朝、後藤鉀二団長が通訳を兼ねていた荻村伊智朗に朝刊を買いに行かせた。「日本から卓球の選手団がやってきた」という見出しの下には日本女子の4名の名前と写真が載っていたが、「他に男子は4名」としか書いていない。男子選手の名前も写真もない。
「それだけか?」と後藤団長。「団長と監督の名前も出てないのか」と怒った。「後藤団長には日本での合宿の時から大変お世話になったけど、こればかりはしょうがない」(江口)。
2年前の1952年のボンベイ大会で日本は世界デビューを果たし、女子団体、男子シングルスの佐藤博治、男子ダブルスの藤井則和・林忠明、女子ダブルスの西村登美江・楢原静と4種目でタイトルを奪い、世界に 「日本のペンホルダー旋風」を吹かせ、戦後の日本の人たちに勇気を与えた。
翌年のブカレスト大会(ルーマニア)は渡航許可が下りずに不参加。そして迎えた54年のウェンブレー大会。日本選手団は2年の間に全員が入れ替わり、若手にスイッチしていたが、イギリスの新聞社は男子よりも女子に注目していたのかもしれない。
江口は渡辺妃生子、田中良子らとともに戦い、女子団体は優勝したが、決勝リーグで1敗しているためにあまり優勝の実感はないと言う。
「トーナメントじゃないし、全勝じゃないから優勝という印象はないんですよ。シングルスでは準決勝で田中良子さんに負けました」
イギリスでは団体戦のエリオット(スコットランド)戦が忘れられないと江口は言う。
「トップで渡辺妃生子さんが負けた。カット打ちのうまい妃生子さんのボールがネットに何本もかかる。完敗だった。あんなに切るカットマンは日本にはいなかった。あの選手と次にやるのかと思ったら恐怖心が襲ってきた。これで自分も負けたら日本は予選落ちだといろいろ考えてしまった。
そこで、もしエリオットがガツンと切ってきたら、その瞬間、前に飛び込んで打つしかないという結論に至ったんです。エリオットはフォアの切れたカットが妃生子さんに効いたから、そのフォアカットをたくさん使ってきた。ホンマ怖かったですわ。気持ちが揺れましたね。でも、回転が多いカットだったけど、少しバウンドが高くなるから、そこを狙うしかなかった」
江口がエリオットに勝ち、日本女子は決勝リーグに進み、優勝した。
一方、イギリスでの対日感情は良くなかった。この大会で、日本への応援は本当に少なかったし、ファインプレーをしても拍手はない。観客はいつも日本の相手を応援していた。「イギリスは紳士の国と聞いていたのに実際には全く違った」と回想する。
日本から炭坑関係の仕事の研修でイギリスに来ていた「中村さん」という方がいて、その人がご飯を炊いておにぎりを選手団に差し入れしてくれた。それを観覧席で食べていたら、『日本人が強いのは石炭を食っているからだ』と新聞に書かれた。
「イギリス人はカリカリにしたパンに牛乳をかけて食べていた。初の海外だし、日本でコーンフレークなんて見たこともなかったから。あれじゃ力が出ないし、差し入れのおにぎりは本当にうれしかった」
ウェンブレー大会は男女団体とシングルスの荻村の3種目優勝で終わり、翌55年のユトレヒト(オランダ)大会は男子団体と田中利明の2種目の優勝だった。「ユトレヒトは悔しい思いしかない。女子は1種目も勝てなくて成績が悪かったから」(江口)。
ツイート