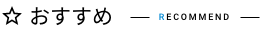<卓球王国別冊「卓球グッズ2018」より>

卓球の用具は、単純な性能の比較だけでは語れない。
なぜこれほどまでに人を魅了し、
奥深き用具の森へと迷い込ませるのか。
『奇天烈逆も~ション』の伊藤条太氏が、
機能美を超えた卓球用具の「美」を、高らかに謳い上げる。
写真=高橋和幸
卓球を始めた中学生の時、初めて買った本格的なラケットは、バタフライの『閃光(せんこう)Z』というペンホルダーだった。グリップの半分ほどに木目がデザインされているやつだ。なぜそれを選んだのかは覚えていないが、友だちの『閃光5』の木目のほうがカッコよく、羨(うらや)ましくて仕方がなかった。木目など打球に関係がないのに。
木材には人を惹きつける何かがある。
ラバーはアームストロングの『プレックスィー』だった。パッケージに、少々場違いな感じの劇画調の青年が描かれたやつだ。なにしろこのラバー、「スピード」「安定性」「回転力」の3項目すべてが満点だというのだから買うしかないではないか(「安定性」とは何なのか今も謎だ)。
胸を高鳴らせて部活に行くと、先輩に「生意気だ」とラバーをメリメリと剥(は)がされた。高性能だったのが気に入らなかったらしい。あの世代の中学生の心身にいったい何があったのだろうか。
ラケットが削って使うものだと知ると、先輩の真似をして、裏の中指が当たる部分を夜な夜な彫刻刀で削っては握ることを繰り返した。専門家の仲間入りをしたような得意な気持ちだったが、ある夜、彫刻刀がラケットの表まで貫通した。これぞ中学生だ。
その後、先輩に前陣速攻型を命じられ、ダーカーの『スピード15』にアームストロングの『赤マーク』を貼った。買った夜、初めて見る表ソフトのツブがどんな素晴らしい作用をするのだろうと思い、表面のザラザラを何度も何度も眺めては球突きをした。あれほど翌日が待ち遠しかった夜はない。
あるとき、工業高校に行った先輩が来て「これを見ろ」と、やたらと古びたラケットを見せた。授業で習った木材を古く見せる処理をラケットに施して「年季を入れた」のだという。ラケットは、使うほどに摩耗して手になじみ、光沢を放つ。木材は劣化していくことさえもが魅力なのだ。
私にはそれが物凄くカッコよく見え、さっそく自分のラケットを汚し、傷をつけたり油をつけたりしてわけのわからない「年季」を入れた。朽ちていく物の魅力に取りつかれた私は、家にあったプラモデルの自動車まで「大破した事故車」に改造し、その持ち主である弟を泣かせた。「このカッコ良さがわからないのかっ!」と説得したが無理だった。
大きくなって比較的簡単に用具を買えるようになると、ラケットは愛着の対象というよりは勝つための道具になり、段々と扱いも荒くなった。
大学時代には、製品名は忘れたがTSPのやたらと細長い合板ラケットを使っていた。あるとき、なんとなく重く感じ、重心を手前にしようとグリップに釘を3本ほどブチ込んだところ、かえって重くなり、わけがわからなくなってしまった。慌てて釘を抜いたり位置を変えてさらに打ち込んだりしているうちに、柄が折れてご臨終となった。
大学を卒業して就職した年、世界選手権ドルトムント大会でスウェーデンが男子団体で中国を破った。男子シングルスでも優勝したワルドナーのプレーを見て完全に脳がショートした私は、すぐにシェーク両面裏ソフトに転向した(その3年前には村上力のプレーを見てペンアンチ反転ロビング型に転向して地獄を見ていた)。ワルドナーは「100年にひとりの天才」と言われていたが、100年経ってないのに張本智和選手が同じことを言われているので「ワルドナーはどした!」と思ったオールドファンは私だけではあるまい。
それはともかく、買ったラケットはニッタクの『ワルドナー』で、ラバーもニッタクの『J.O.ワルドナー』だった。自分に合うもクソもない。ワルドナーとついていれば何でもよかった。ほどなく、ドライブができないのであきらめて両面表ソフトにして、どこがワルドナーだかわからなくなってしまったが、心はいつもワルドナーだった。そのラケットは今はどこかにいってしまった。あんなに気に入っていたラケットだったのに。
それにしても卓球の用具は美しい。
ペンホルダーの桧単板には、木曽谷の北側斜面で育った年輪の詰まった樹齢三百年以上の桧だけが使われるという。卓球が生まれてまだ百年ちょっとだ。今ラケットになっているのは、卓球がまだ影も形もないころに生まれた桧なのだ。これから生まれる桧がラケットに使えるようになる頃、今この文章を読んでいる人はもう誰もいない。

木曽桧単板のラケット。木目が美しく、素敵な匂いがする
その頃、まだ卓球はあるだろうか。
そんな遥かなる時間の芸術品を使うラケットとは、なんと贅沢なのだろう。以前バタフライから樹齢三百五十年の最高級木曽桧を使ったラケットが二百本限定で発売されたことがある。その名も『ヴィンテージ2001』。うやうやしい漆塗りの桐箱に入っていて1本4万円だった。恐ろしくてとても削れなさそうだが、買った人は使ったのだろか(ちなみに蘇州の世界選手権のメーカーブースで見たあるラケットは、一本二十万円もしたが、それはグリップにダイヤモンドが埋め込まれていたのだった。……それはちょっと違うだろ)。
ラケットを削ると、なんともいえない木の香りが漂う。香りの正体は「テルペノイド」と呼ばれる揮発性物質で、細菌を殺す能力があるという。もともとは植物が生きのびるために身につけたものと言われるが、人間はこの香りを嗅ぐと気持ちが落ち着く。人類の祖先が、かつて森林をその住みかとしたことの名残りだ。木材は、何十万年にもわたって人類のパートナーだったのだ。
だから木のラケットには愛着がわく。要らなくなってもそう簡単には捨てられない。卓球のラケットは愛玩(あいがん)用具なのだ。
ラケットが愛玩用具だとすれば、ラバーは魔性の用具だ。中でも裏ソフトは神秘的だ。ボールをグリップする摩擦力と、はじき返す弾性が、一分間に一万回転という途方もない回転を生み出す。インパクトの瞬間にボールがまったく滑らないという、異常な摩擦力の用具を使う球技は卓球だけだ。
ラバーの主成分である天然ゴムは、東南アジアに生息するゴムの木の樹液から作られる。樹液そのものは液体だが、水分を取り除き、熱と硫黄を加えると弾性を持つようになる。こうしてできるのが天然ゴムだ。
パッケージを開けた時に鼻をつく臭いは、ゴム原料そのものと硫黄(いおう)、そして製造工程で加えられる様々な化学物質の臭いだ。卓球のラバーは、現代化学工業の結晶なのだ。
これらの臭いは一般的には不快なものだが、卓球人にとっては違う。真新しいラバーの臭いは、素晴らしい食い込みと摩擦力を予感させる胸躍る臭いなのだ。この臭いに酔いしれることができるのは、ラバーの魔性に魅入られた者の特権(あるいは中毒)だ。下手すると、ラバーの臭いから商品名を言い当てることができるマニアさえいかねない。そういうバカ者を集めて「利きラバー大会」を開いてみたらどうだろう。「ええっと、これはテナジー05の黒、製造時期は2015年の冬です」という具合だ。何の役にも立たないどころか、メーカーにとっては面倒な客を増やすことになるだろうが、市場の活性化のカンフル剤としてどうだ。
本当にそういうマニアがいるのではないかと思わせるほど、ラバーの魅力は卓球人をとらえて離さない。
はるか東南アジアから旅をしてきたゴムの原料は、化学技術の粋を集めた製造工程を経て、人工的な表面と幾何学的な粒形状を与えられて美しい製品となり、最後に一本のラケットと出合う。自らの遠い親戚ともいえる木材のラケットに。
そしてしばしの間、神秘的なまでに凄まじい性能を発揮して、その役割を終える。
ラバーは儚い。儚(はかな)いがゆえに美しい。その美しさを味わうために我々は、ときに必要もないのにラバーを買う。
このようにして増えたラケットとラバーを眺めながら、春の夜は更けていく。
卓球の用具は美しい。
ツイート