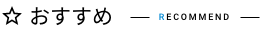去る10月25日に83歳で逝去された元全日本チャンピオンの渋谷五郎さん。
太く短い選手生活、そしてその後、明治大卓球部の監督として活躍された渋谷さんを偲んで卓球王国が2013年5月号で掲載した「伝説のプレーヤーたち 渋谷五郎」を紹介。日本卓球界の偉大な先輩のご冥福をお祈りする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔昭和34(1959)年度全日本選手権優勝〕
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
指導者はいない、技術書もない。
それでも1年365日、
欠かさずにラケットを握り続け、
カットと攻撃を融合させた、
独自のスタイルを築き上げた男。
「シェークハンドラケットを使用した
史上初の全日本チャンピオン」
その称号は永遠に
渋谷五郎とともにある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インタビュー=今野昇・柳澤太朗
写真(p.151)=今野昇
写真提供=渋谷五郎
「自分を変えなければ伸びない。現役時代は常にそう思っていた。自分を変える努力が必要だという意識があった。
選手というのは、新しいことをやるのに抵抗を感じやすい。もしかしたら、自分のプレーがおかしくなってしまうんじゃないかと考えてしまう。でも、変化を恐れていたら未来はないんだよ」
雪国・津軽はこういう人も生むのである。相手の強打を耐え忍ぶ、粘りが身上のカットマン。そんなイメージと先入観は、ものの見事に打ち砕かれる。
ペンホルダーが当たり前の時代に、ひとり敢然とシェークハンドラケットのカットスタイルに挑み、築き上げたのは打球点の早い独創的なカットスタイル。しかもカットやツッツキと同じフォームから、突然攻撃へと転じ、対戦相手を混乱に陥れた。
しかし、パイオニアの自負も気負いも、この人からは感じられない。どこか飄々として自然体、そしてスマートだ。
昭和34(1959)年度全日本選手権の天皇杯保持者。シェークハンドラケットを使用した初めての全日本チャンピオン、渋谷五郎。
太く短く競技人生を駆け抜けた異才の人は、話を聞いたこの日、関東の学生選手たちを引率する恒例のスウェーデン遠征から帰国したばかりだった。
1937(昭和12)年9月30日、その名前が示すとおり、6人兄弟の5番目として生を受けた渋谷五郎。生まれは秋田県だが、すぐに青森県に移住。青森市の郊外にある西田沢村で少年時代を過ごした。
山沿いにあった社宅に住んでいた渋谷は、海沿いにある小学校まで、2キロ余りを歩いて通わなければならなかった。雪深い津軽の地。冬に大雪が降ると、学校に向かう途中の田んぼは道がなくなり、一面の銀世界になる。電信柱を目印に、腰まで雪に埋まりながら2キロの道のりを歩いた。学校が終わって家に帰ってくれば、重い軍隊式のスキーを担いで裏山に登り、スキーに興じた。
「雪国の青森で育ったのも、運が良かったかもしれない。自然に足腰が鍛えられたし、それを苦痛とも思わなかった。何が幸いするか、わからないね」
小学3年生くらいの頃から遊びで卓球をやっていたが、本格的に卓球を始めたのは地元の西田沢中に入学してから。それでも、指導らしい指導は受けず、自分たちで遊びながらやっていた。
なぜ、カットマンになったのか。学校にかつて東北選手権で優勝した先生がいて、その人がカットマンだった。カットしたボールが、ネットの手前でフワリと浮き上がり、相手コートに入る。そのカットの飛行曲線に魅了された。
なぜ、シェークハンドラケットを選んだのか。理由は単純に「珍しかったから」、人と違うことがしたかった。
「当時は岩手の藤井基男さんと、地元では青森商業高から早稲田大に進んだ宮本良男さん。現役でやっていたシェークの選手は、そのふたりぐらいだった。
最初はペンホルダーで、何となくカットをやるようになっていたけど、カットはシェーク、シェークはカットというイメージもあった」
もちろん、シェークハンドラケットが簡単に手に入ったわけではない。ラケットの善し悪しなどと贅沢を言っていられず、「シェークの形をしていればいい」という時代だった。当時最先端だった一枚ラバーも手に入らず、サンドペーパーも貼ったし、何も貼らない木べらも試した。
当時の青森は誰もが認める「卓球王国」であり、同時に「カット王国」でもあった。全日本学生5連覇の「球聖」今孝、日本初の世界王者・佐藤博治というカットの大先輩も青森県出身。「全国で勝つのはカット」という雰囲気が、青森の卓球界にはあった。
ペンカットの選手を参考にして、見よう見まねでシェークカットに取り組んだ渋谷少年。雑誌やビデオもない時代、自分ひとりで工夫するしかなかった。夏休みには農作業で卓球をやる人がおらず、近所の女の子に「おい、卓球やろうよ」とお願いするような練習環境。おかげで弱い相手でも自分の練習をする術を覚えた。中学2年の県大会では決勝まで進み、黒石中3年の成田静司に敗れた。
渋谷の1学年上の成田はペンホルダーのカットマン。後に昭和32年度、33年度と全日本選手権2連覇。「成田さんは天才だった。カットも攻撃も本当にきれいなフォームだった」と渋谷は言う。
高校は中学時代から練習に参加していた県下有数の進学校・青森高校に入学。中学3年の時に県大会決勝で敗れた、古川中の村上輝夫がチームメイトになった。後に、村上は渋谷と組んだダブルスで全日本を制し、59年世界選手権では荻村伊智朗とのペアで男子複優勝。世界代表クラスの選手の名前が次々に出てくる。それが卓球王国・青森の実力だった。
青森高校の練習時間は短く、卓球場は夜間に照明が使えない。冬になると練習できるのは1時間半ほど。そこで夜間は近隣の実業団の強豪・青森営林局へ出稽古に行った。卓球部の顧問である木村滋男先生の妻、正枝夫人が理事長を務めていた青森山田高で、週末や夏休みに合宿を行うこともあった。
県下には成田が進学した弘前高、青森商業高、八戸高など全国でもトップクラスの強豪校がひしめいていた。1・2年の時にはインターハイ予選を突破できなかったが、逆に県予選を通れば、全国でも上位進出が約束されたようなものだった。
「青森はカットが多いから、攻撃の選手もカット打ちが非常にうまい。青森で、カットで代表になれれば、全国でも勝てるという感じだったね」
同期の村上も、後にカット打ちの名手として名を馳せたが、渋谷は村上と練習する機会は少なかったという。「高校時代もそうだし、大学に入ってからも、年に2回くらいしかやらなかった。村上とやると1試合で1時間以上かかる。本当に厳しい試合になるから、彼とやるには相当な覚悟が必要だった」。
高校時代の成績は、高校2年で全日本ジュニアベスト8、高校3年でインターハイベスト8。高校2年の国体で全国デビューを飾ったが、国体の強化練習会で受けるプレッシャーは並大抵のものではなかった。
「青森は卓球で勝たなければいけない、という時代だった。強化練習会でもプレッシャーで金縛りになったような感じだった。大先輩がズラリと並んで、ミスをしようものならすぐ怒鳴られる。本当に怖かった」
インターハイでベスト8に入っても、渋谷の大学進学はギリギリまで決まらなかった。経済的な事情を考えると、実業団への就職も現実的な選択。しかし、母親が「自分が働いてでもお金を出すから」と言ってくれたおかげで、高校3年の秋にようやく大学進学が決まった。
青森高から明治大に進んだ津内口弘志に中学時代から世話になっていたこともあり、村上とともに明治大に進学。当時、関東学生1部の下位校だった明治大は、ふたりの入学を待ちきれなかったかのように秋季リーグで2部へ降格。関東学生リーグは2部でのデビューとなった。
ツイート