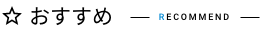1960(昭和35)年3月に明治大を卒業し、九州・福岡の八幡製鉄に就職した渋谷。
八幡製鉄には元世界王者の田中利明も在籍し、一緒に練習できると思って入社したが、卓球部の練習には全く姿を現さなかった。全日本チャンピオンなのに、練習相手がいない。仕方なく、高卒の選手たちに「ドライブはこうやって打つんだよ」と教えていくしかなかった。
東京ははるかに遠く、母校の明治大に練習に行くわけにもいかない。61年の世界選手権での代表入りを目指して、レベルの高い練習を求めた渋谷は、大阪に住んでいた星野展弥に連絡を取り、週末に大阪まで夜行列車で往復するようになる。明治大OBの渋谷と専修大OBの星野。ライバル校のOB同士でも、仲の良いふたりだった。
金曜日の夜に福岡を出発して、土曜日と日曜日は星野と厳しい練習。日曜日の夜に大阪を発って、夜行列車でまた福岡へ戻るという生活。社会人1年目、2連覇がかかった全日本は3位。準決勝で練習相手だった星野に当たって敗れたが、初めて世界選手権代表に選出された。
渋谷五郎にとって、最初で最後の世界選手権となった、1961年の世界選手権北京大会。
卓球ニッポンの看板を背負い、羽田空港から香港へ発つ時の心境は悲壮なものだった。「勝てなかったら、もう日本には帰れない」。
そして、自分にとってのピークであった大学4年生時と比べると、技術だけでなく、体もベストの状態ではなかった。出発の1週間前の合宿で、体操中に背筋を傷め、突然右肩が上がらなくなった。
「長谷川喜代太郎監督が『すぐ医者に行け』と言うんで、すぐに野球の読売ジャイアンツのトレーナーだという方のところに行って、診てもらったりした。北京へ向けて出発して、香港で地元の選手たちと練習するまで、しばらくラケットを握らせてもらえなかった。
この時はつらかった。もう北京には連れて行ってもらえないんじゃないかと思った。もともと、毎日練習しないと気が済まないほうですから」
それでも何とか大会本番には間に合わせることができたが、北京大会のプレー環境もまた、ベストにはほど遠いものだった。
「北京大会の時の床はすごかった。あれはひどかったね」
ワックスをかけたばかりの、まるでスケートリンクのように滑るフロア。日本選手のフットワークを封じた北京・工人体育館のフロアは、今でも語りぐさになっている。「ストップを取ろうとしたヨーロッパのカットの選手が、台の下を潜って向こう側から出てきたからね」。まるでホラ話のような、本当の話だという。
国家の威信を賭けて戦う中国選手たちは、1万5千人の観衆の大声援をバックに、強烈なスマッシュを何本も打ち込んできた。男子シングルス4回戦、ベスト16入りを賭けた試合で渋谷が対戦したのは李富栄(中国)。
出足から若さみなぎるスマッシュで攻める李に、必死で食らいついた渋谷。「これ以上こんなペースで打たれたら、『もう死ぬわ』と思った」。それくらい李の連続スマッシュは強烈だった。しかし、さすがの李もオーバーペースだったか、途中でドライブからの強打を狙う作戦に転じる。ようやく少し楽になり、競り合いながらも2ゲームを先取した。
勝利まであと1ゲーム。しかしここで、李が再び作戦を切り替える。ツッツキとショートを主体にして粘り、チャンスボールだけを強打で狙ってきた。
「ツッツキを打つのが好きだったから、どんどん打っていった。でも、もう全盛期のボールじゃなかった。巡り合わせだからしかたがないけど、本音を言うと、やっぱり大学4年生の時に世界選手権でやりたかった」
第4ゲームは19-21まで競り合ったが、最終ゲームは大量リードを許し、8-21で敗れた。19歳の李に中国卓球の技術と戦術の幅広さを見せつけられた。
完全燃焼とは言い切れない北京大会。大会を終え、日本に帰ってきてからも練習は続けたが、何よりも大事な、プレーヤーとしての「欲」がなくなってしまった。
中学生で卓球を始め、県大会で2位になってから10年。そのカットスタイルが、わずかな打球点のズレで感覚を失うほど精緻なものであったように、競技人生のピークもまた短く、到達点の高いものだった。
そして、その鋭いピークの先端は、二年に一度の世界選手権を指すことはなかった。実業団で30歳を超えてもプレーする選手がいる現在とは違い、学生卓球を中心として、誰もが短く、そして激しく、競技人生を燃焼させていた時代。
「まだ24歳。今から考えてみると若かったね。でも、自分としては世界選手権にも1回出られたし、『もうやりきった』という思いが強かった」
63年プラハ大会、続く65年リュブリアナ大会。卓球界の覇権を巡る日本と中国の激しい争いの中に、渋谷五郎の姿はなかった。
ツイート