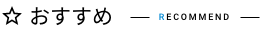伊藤美乃り

卓球の世界では、そのプレースタイルが年々変化し、進化している。多種類の用具を使う卓球で、異彩を放つのは伊藤美誠(スターツ)だ。
ドライブ打法という安定と威力を持つ打法とプレースタイルが主流の中で、バック面にスピード系の表ソフトを貼り、フォアの回転系の裏ソフトではドライブはもちろんだが、スマッシュというリスキーな打法を駆使し世界で活躍している。
その独創的な発想と卓球は、なぜ生まれたのか。
それは美誠がお腹にいる時から胎教として卓球を教えていたと言われる伊藤美乃りさんに行き着く。
今年、伊藤美誠選手(スターツ)の母、伊藤美乃りさんが『自分らしく生きるために』(スターツ出版)を上梓した。
伊藤美誠選手がお腹の中にいる時からまさに胎教のごとく「卓球選手」として育て、ラケットを握り始めてからも二人三脚で世界への階段を上がっていった親子鷹。特に美乃りさんの真っ直ぐで独自の思考と躾(しつけ)があったからこそ、「伊藤美誠」という規格外の選手になったのは間違いないだろう。
以下がこの書の章立てだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『自分らしく生きるために』
第1章 自分にとことん向き合う
第2章 冷静な目を持つ、本質かどうかを見極める
第3章 自分が成長する環境を作る
第4章 周囲の人で人生が変わる
第5章 大切なのは精一杯の愛情
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
伊藤美誠という子どもが、生まれながらに特別だったのか。それとも伊藤美誠という選手が母・美乃りによって育てられた選手なのか。
何度もインタビューをすれば、伊藤美誠の奔放な発言、自由な発想は天性のものかと思ってしまうのだが、そのあとに母・美乃りの話を聞くと、この母が「美誠を自由奔放に育てた」ことで卓球も独創的な形になり、枠にはまらないものになったことがすぐにわかる。母の言葉が娘・美誠に伝わり、発する言葉にもなっている。それは娘が暗示にかかっているのでもなく、母の自由で一本筋の通った考えが娘の環境を作っていったのだろう。
伊藤親子と松﨑太佑コーチの「チーム伊藤美誠」は、個性的で個人を尊重する「伊藤美誠・美乃りシステム」と呼べるものだ。これはかつて福原愛が個人事務所でまわりを固めて「チーム・フクハラ」を作ったやり方の踏襲でもあり、さらにスターツという大手企業がバックについて、より強固なものになっているとも言えるだろう。中国のような国家体制で選手たちを強くしていくやり方ではない、日本独特のやり方だ。
この書籍の内容に関しては、書き出しで、著者・伊藤美乃りがこう記述している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本書では、私なりに考え実践し、さらに美誠に伝え続けてきた“人として生き抜くためのスキル”を紹介しています。中にはオリジナリティが強すぎて、みなさんの生活に落とし込むには難しいこともあるかもしれません。しかし、私は思います。人生は、まさに「生き残り大作戦」。だからこそ、明るく強く、自分らしく楽しんだ者勝ちだと。
今の生き方に迷いを抱えている方々の、生き抜くヒントになれば幸いです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卓球王国は著者の伊藤美乃りさんにインタビューを行った。
●――五輪が終わってから本を出そうと思ったのですか? それとも、その前から?
美乃り:本を書く準備というより、美誠が20歳になったら伝えたいことを小さいときから書き留めてたんですね。それを吐き出したって感じです。
●――伝えたかったことはどういうことでしょう。美誠ちゃんに語りかける感じなのか、卓球をやっている人、やってない人の心にも届くようにメッセージをぶつけた感じなのか?
美乃り:美誠が関わっていく中で、大切な人だったり仲間だったり、美誠が自分の何かを伝えたい人ができてくると思うんですよね。私の思いを美誠に受け継いでもらって、その美誠がまた他の人に受け継いでほしいことを書き留めたという感じです。
●――書かれてる内容というのは、「チーム伊藤美誠」の中で共有されてるものが書かれてるんですか? それとも美乃りさん個人で別の思いがあるのでしょうか?
美乃り:私が生きてきて、いろんな方に出会って、松﨑さんとの出会いで衝撃を受けた部分もありますし、自分自身が変わった部分もありますし、その中で今後伝えていきたい、自分がいなくなった後も美誠に、そして美誠が大切な人に伝えていってほしいことだったりですね。巻物みたいなものを残したくて書き留めたんですよ。それが本になった感じです。
●――伊藤家直伝のみたいな?
美乃り:そうです(笑)。「美乃りの子孫に受け継ぐ魂」みたいな(笑)。
●――こういうことは、普段美乃りさんが美誠ちゃんに話かけたり、ディスカッションになったり、そういうことがこの本に詰め込まれてる感じでしょうか。
美乃り:それもありますね。
●――普通の親子関係で、なかなか自分の思いとか考え方を子どもと話すことってない気がします。
美乃り:例えばニュースを見てたり、目の前で何かしら出来事が起こった時に「どうなの?」って聞いてみたりした時から始まる気がしますね。リアルなものを突きつけられた時に私が本音で言って、それに対して美誠も自分の意見を言う、という感じですね。説教じみたものではなく、すごいフランクな状態ですね。何か目の前で起こったことに対して会話が進んでいる感じです。
●――美乃りさんが書き留めることのは、美誠ちゃんの成長とともにインスピレーションが出てきて書き留めているのでしょうか。それとも、さっき言ったみたいなリアルなものを美乃りさんが感じた時にそれを書き留めてるんでしょうか。
美乃り:美誠との間であったことを書き留めることもあるかもしれないですけど、それよりもその時に感じたことでしょうか。世の中で起こってることだったり目の前で起こってることだったり、それに対して今美誠に伝える必要はないけども書き留めておいて将来美誠に感じてほしいことだったり、20歳になったら感じてほしいことだったり、自然と受け継いでいってほしいことを書き留めています。
●――卓球と向き合うということは伊藤家にとっては人生に向き合うことと同じですね。内容的には卓球による経験をベースにして、そこに通じる部分が書かれていますね。
美乃り:「卓球をやってきたからこういう考え方が出てきたんですか?」と聞かれた時に「そうです」とは言えません。私の中で卓球が生活であり人生なので、普通に生きてきた私の人生において「これが感じたことです」というのが答えです。つまり人生が卓球なんですね、だから「卓球の中で感じたんですか」と聞かれると、「えーと、どうだったかな」となる。私の中で卓球が「卓球」という言語じゃなくなっているのだと思います。
●――美乃りさんが前に「デザインしていく」という言葉をよく使っていて、美乃りさん自身も日本の中で生きづらい部分も多いと言ってましたね。そういう「日本人らしくない」考え方や発想があるから伊藤美誠というある種規格外の選手が育ち、スケールが測れない選手になっている。そこが不思議であり、面白いですね。美乃りさん自身も日本で生まれたじゃないですか。
美乃り:そうですね、何なんですかね。
●――美誠ちゃんはわかるんですよ。だって、普通でない、美乃りさんが育てているから。でも、なぜ美乃りさん自身がそういう発想になっていくのか。この書籍に書かれている文言もそうだけど、飾りがなく、直言ですね。普通は自分をよく見せようと飾るじゃないですか。
美乃り:(飾ったことを言うのは)気持ち悪くてしょうがないですね。
●――親だったら「期待に応えなさい」と言うものなのに、いい意味で裏切られる言葉が多いですね。
美乃り:刺激があって面白いですよ。期待に応えない子どもなんて最高じゃないですか。
●――普通は周りの評価を気にするとか、日本人としてそういう価値観があります。
美乃り:例えばですけど、日本で素敵だなと思うのは日本のお城や文化遺産、宗教的な行事とかは美しいとか素敵だなと思いますけど、理解に苦しむ部分も時々ありますね。
●――タイトルは誰が考えたのですか?
美乃り:編集の方が私と話をする中でつけたものですね。
●――まさにこのタイトル『自分らしく生きるために』は美乃りさんなんですか?
美乃り:そうですね。最初に出した本が子育て層に語りかける内容だったんですけど、今回はビジネスマンとか社会で戦っている人にも、スポーツで戦っている人の思いが当てはまるのかなと思いますね。
●――社会で生きているビジネスマンはアスリートとほとんど共通するとも言えますね。
美乃り:それも感じました。
●――特に好きな項目は?
美乃り:「愛情があるからこそ何者にでもなれる」というところですかね。美誠のためだったら何者にもなれるって思います。自分の強い信念ですね。愛情が濃すぎますね。濃いなって改めて思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昨年の10月、まだ東京五輪の熱気も冷めやらぬ時に卓球王国は伊藤美乃りさんにインタビューを行っている。母親としての強い愛情を持ちながら、伊藤美誠の最大の理解者であり献身的に支える伊藤美乃りという女性は、強い意志を持った女性だった。「小さい頃から美誠自身が自分で決めて、自分で痛い目にあって、自分で責任を取る。自分で歩かせて自分で怪我をする。怪我する前に止めたことはないです」と語った、母・美乃り。覚悟を持った人である。
その彼女の信念、思考方法の発露が、『自分らしく生きるために』の中に詰め込まれている。火傷をするようなヒリヒリとした言葉が飛び交いし、現在、子育てをする人、子どもたちの指導に関わっているコーチの方が読むと、彼女の言葉が胸に突き刺さり、このままじゃダメだ、子どもたちのために頑張らなければ、という気持ちにさせる一冊かもしれない。

スターツ出版から上梓された『自分らしく生きるために』を手にする著者の伊藤美乃りさん
ツイート