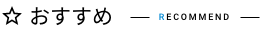1971年世界選手権名古屋大会の混合ダブルスで優勝した張燮林。左はパートナーの林慧卿。6年ぶりの世界選手権だった
65年リュブリアナ大会以後、66年に政治・権力闘争である文化大革命が始まり、黄金時代を迎えていた中国は国際舞台から姿を消し、67年、69年の世界選手権大会に参加しなかった。中国国内は混乱を極め、容国団や他の卓球仲間が自殺する事態に陥っていた。
そして、世界最強軍団が復活するのは71年名古屋大会であった。この大会をきっかけに中国とアメリカのピンポン外交が始まり、中国卓球は再び世界の覇権を握っていく。
●●●●●●●●●
文革当時、国のスローガンは「為工農兵服務」(工場労働者、農民、軍兵のためにサービスを提供しましょう)だった。私たちは常に全国各地を巡業して、卓球ショーを現場の人々に披露していた。そういうわけで卓球を続けることができた。
世界選手権に出られなかったのはマイナスですね。政治的な原因ではあったけど非常に残念だった。自殺した傅其芳、容国団、姜永寧は中国卓球界の誇りだった。傅其芳、姜永寧は私たちの大先輩だし、容国団と私は同世代のチームメイト、かつルームメイトでもあった。悔しかった。文革という政治運動に対し、私自身も他の人もなかなか理解できない状況だった。
71年の名古屋大会へは選手の誰もがすごく行きたがっていた。私たちは皆、新しい中国に育てられた選手だし、祖国の栄光のために奮闘したいと思っている。しかし、造反派の一部が試合参加を反対していたのも事実だ。私たちは参加するための理由書を書き上げ、中央政府へ送った。周恩来総理が指示を与えてくれたと同時に、毛沢東主席にも報告してくれた。最終的に、毛沢東主席が大会参加の指示を与えてくれた。
その当時は、政治的な雰囲気や日中関係もあまり良くなかったし、日中がまだ国交を樹立していない時代だからね。日本の右翼の勢力も大きいと伝えられていた。だから、中国選手団の名古屋大会への参加を導いてくれた後藤鉀二(当時日本卓球協会会長)さんに感謝しなければならない。何度も中国へ来て、周恩来総理と面談してくれた。最後に、毛沢東主席の指示があった。「我がチームは行くべきだ。困難に負けず、死をも恐れずに」と。
困難に負けずとは、どんな難しい試合にも粘り強く戦うこと。死をも恐れずとは、覚悟を持って試合に臨みましょうという意味だ。当時は、右翼が極端なことをやりかねないという状況だった。
名古屋大会には混合ダブルスだけ出場し、優勝した。混合ダブルスにエントリーした日本人選手は16組もいた。16組もいるから、優勝できそうなものだ。日本は人海戦術を利用して、よっぽど混合ダブルスで優勝したかったんだろう。名古屋から2年後の1973年のサラエボ大会が、私の選手として最後に参加した大会だ。
73年を最後に現役を退き、同時に張燮林はコーチ、そして女子の監督として中国チームを率いていくことになる。彼こそが、現在の中国女子の強さの礎を作った男だ。75年世界選手権から、91年千葉大会でコリアに敗れるまで、女子団体8連覇を成し遂げた。
取材をした昨年(2012年)12月の中国・杭州でのワールドツアー・グランドファイナルでも彼のまわりには弟子、孫弟子が多く集まっていた。信頼と尊敬を集めているのは70歳を超えた今も変わらないようだ。
●●●●●●●●●
私は光栄と幸運を感じている。他のコーチが大体失敗によって指導者を卒業するが、私は幸運だった。ずっと選手たちが頑張って、チャンピオンを続けて取ってもらった後に、監督の座を後任の陸元盛に譲った。ずっと卓球を選んできた私の人生は卓球とともに歩いてきたけれど、重圧からも解放され、胸をなで下ろした。
中国も卓球を通じて、アメリカとの関係を発展させ、国のドアを開いて、お互いを迎えることができた。これがピンポン外交だ。 私も代表団の一員として、アメリカに訪問した。
選手としても、世界チャンピオン(団体・ダブルス)になった。いろいろな面で、卓球が私自身に栄誉をくれた。たくさんの卓球愛好者からの尊敬ももらったことをとてもうれしく思っている。卓球の会場へ来るたびに、長い付き合いのたくさんの友だちや教え子たちに会える。もちろん今では弟子だけではなく、孫弟子もいる。卓球に対する自分の努力が無駄にはならなかったなと思う。
国も我々のことを忘れなかった。私は、2008年に開催された北京五輪の旗手を務めさせていただいたり、建国60周年の国慶節ではパレードにも参加させていただいた。国と国民の尊敬を受けて光栄だし、とてもうれしかった。本当に大満足だね。
73年で選手を退いた後は、最初はコーチだったが、その後、監督を務めた。最後は95年天津での世界選手権。天津大会の後、正式に卓球とバドミントンの競技強化管理センターの副主任(副センター長)に就任した。
96年アトランタ五輪の時、鄧亜萍の調子が良くないからと、いったん女子チームに呼び戻された。ひとつの目的は、鄧亜萍の大会前の調整。もうひとつの目的は、大会への準備に向けて、陸監督のサポートだった。その大会が終わってから、すぐに管理センターに戻った。
良い成績を自慢してもあまり意味がない。中国女子が基本的にずっと優位を占めているから、勝つのは当たり前のことだ。
ただし94年の広島のアジア大会の時、鄧亜萍が小山ちれに負けた試合では何かしこりが心の中に残っているし、納得できなかった。悔しいのはその試合の雰囲気や、小山ちれの上品でない行為のためだけでない。反省すべきなのは、私が選手の細かい管理ができなかったこと。指導が足りない私自身の責任についてだ。
その日、まず喬紅と小山ちれの試合があった。喬紅も小山ちれに負けたことはなかった。鄧亜萍が私の後ろに座っていたのだが、ほかの人とワイワイ歓談をしていた。私が彼女に注意し、試合を見て、相手の長所や短所を小まめにチェックしておくようにと指示した。しかし、後ろのしゃべり声が絶えることはなかった。そして、喬紅が敗れた。その後すぐに、鄧亜萍と小山ちれの試合が始まった。その時、鄧亜萍は頭と気持ちの切り替えがすぐにできなかっただろう。その試合は長年のコーチの経験の中で、私が受け止めるべき教訓だと思っている。
負けたという結果に関して、選手には責任がない。責任はすべてコーチの私にある。台についた鄧亜萍はもちろん力を尽くしたし、全力で戦っていた。ただ、鄧亜萍は小山ちれに対して怒りながらコートに立ち、試合中に冷静さを失っていた。選手の気持ちを整えてあげられなかったのは監督の責任なのだ。
91年千葉大会では、女子団体でコリアに負けた。試合で問題だったのは、あの時のスウェーデン人の審判だった。鄧亜萍のサービス5本のうち2、3本を違反としてフォールトと判定した。鄧亜萍は、いつも使っていた得意なサービスをやめ、バックサービスだけを使うことになってしまった。彼女の技術のコンビネーションが少なくなり、サービスの判定によって大きな影響を受け、敗れた。
私は、試合後その審判に厳重にこう抗議をした。
「鄧亜萍は今までずっと同じサービスを使っていたし、世界チャンピオンになったのも1、2回ではない。それまでたくさんの試合の中で、一度もサービスをフォールトと言われたことがない。今日、初めて君だけに言われたのはなぜだろうか。今までの審判がみんな君よりレベルが低く、常に間違えていたのだろうか」
また、96年アトランタ五輪の決勝、鄧亜萍対陳静の試合。鄧亜萍が中国を代表し、陳静がチャイニーズタイペイを代表していた。政治的な意味も入っているから、緊張した一戦になり、負けられない試合だった。試合中に会場で騒動が起きてしまったりと、大変な状況で、この試合は私にとっても、すごく緊張した試合として記憶に残っている。
88年ソウル五輪の時、私が陳静を起用し、何智麗(小山ちれ)を落としたことで、当時すごい騒ぎが起きたが、結果として、最後に五輪会場に中国国旗が3枚揚げられ、金銀銅のメダルをすべて収めた。その陳静とアトランタ五輪では戦った。それは何かの因縁だったのか。
我が国は国家体制として卓球というスポーツを支えている。選手たちは後顧の憂いを持たずに、勉強しながらも卓球に集中することができる。代わりに卓球チームは祖国の栄光のために頑張る。中国卓球の理念や指導法は、昔からの伝統として代々受け継ぎ、今もその道を歩み続けている。私たちが持っていた伝統や指導方法、指導理念などを、その後の若手監督やコーチに受け継いでもらったことを誇りに思っている。
中国のサッカーなどは自分たちのシステムを持っていない。中国の卓球には自分たちの道があり、私たちが整え、システム化した伝統的な強化方法を、その後発展させてくれた。
卓球の技術の創新や進歩などは非常に速い。今の卓球を見ても大きく変化したことがわかる。そして選手の意識はより積極的に、主動的になった。それは昔の私たちの時代より強いものだ。今の選手たちは大胆で、思い切って全力で戦う。その戦いぶりは、当時の私たちよりもっと際立っている。時代は変わる。世界の卓球も時代とともに変化していくものだ。 (完)
「63年プラハ大会のシングルス準々決勝で荻村さんと当たった。
それは知力を闘わせた試合だった」
「最後に、毛沢東主席の指示があった。
『我がチームは行くべきだ。困難に負けず、 死をも恐れずに』と」

1989年世界選手権ドルトムント大会で8連勝を決めた中国女子。中央が張燮林監督

1991年世界選手権千葉大会の団体戦、鄧亜萍(背中)と高軍(右)にアドバイスを送る張燮林監督
チャン・シエリン
1940年6月25日、中国・江蘇省生まれ、上海で育つ。1961・63年世界選手権シングルス3位、63・65年の世界選手権団体優勝に貢献し、63年に男子ダブルス、71年に混合ダブルスでそれぞれ優勝した。72年に女子コーチに転身し、75年からの団体8連覇にコーチ、監督として貢献。95年天津大会まで女子監督を務めた
ツイート