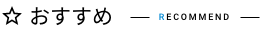バタフライのチェンジはまだあった。まず15年4月にラケットのラインナップを大幅に変えた。多くの商品を廃番にしながら、木材だけの『ハッドロウ』、カーボンなどの特殊素材を入れた『ガレイディア』、そして『インナーフォース レイヤー』というラインナップに絞り込んでいった。これは類似商品が多くなりすぎ、品番が多くなった部分を整理し、ラケットデザインの統一を図るためと言われている。国内での品番が半分近く減ったことで、生産効率も上がっていった。
さらにチェンジは続く。15年の10月のタマスの展示会では斬新なアイデアで関係者を驚かせた。それはラバーパッケージの一新だった。
黒地の真ん中にはホログラム(特殊なフィルムやプラスチック板の上にレーザービームを使って立体画像をプリントしたもの。光線をあてると,立体画像が再現される)を使ったバタフライマーク。その周りを様々な色の放射状の円が何重にも囲っていく。商品ロゴは上部にある白抜きでローマ字のみ。それぞれの商品のパッケージは色の組み合わせの違いだけで表現している。これを見た瞬間、デザインのインパクトがあった。一方で、「絶対批判を浴びる」と直感した。
実際にお店からはそれぞれの商品がわかりにくいと批判の声があがった。確かに色の違いだけのパッケージだから、今までのようにテナジーはこのパッケージ、スレイバーはこのパッケージという明らかな違いは、商品のネームを見ない限りはわからない。
また今まではウインドウと呼ばれる小窓がパッケージの横にあり、そこでラバーを見たり、触ることができたが、新パッケージにはない。一見すると全部が同じラバーのようにも見えるが、お店に並んでいればひと目でそれがバタフライラバーであることがわかる。
「数十回の試行錯誤やアイデアがありましたが、最終的にはサークル(円)を使ったものにしました。ブランディングとデザインが優先順位の上で、ラバーの情報は下位になっています。そのために従来あった小窓や、厚さや色のシールもデザインを邪魔するので作りませんでした。まずは他社との差別化を図り、お店に並べた時にバタフライのラバーは一目瞭然でわかります。社内での調整にも時間をかけ、基本のデザインを決め、あとは商品別に色のバリエーションで展開しようと最初から決めていました」(パッケージデザインを担当したタマス社・マーケティングチームの山崎剛志)
今までテナジーなどバタフライ商品は偽物などのコピー商品がタマス社の頭を悩ませていたが、「当社ラバーの偽物も多く出回っており、パッケージの変更は偽物対策の一環でもあります。中央のロゴに施したホログラムと精緻なデザイン、高度な印刷技術は簡単に真似できるものではありません。これは消費者保護の観点からも必要でした」と山松氏は語る。

2015年9月までの旧パッケージ

15年10月にリニューアルされたラバーパッケージ。「どれも似ている」との批判もあったが、他メーカーと完璧に差別化された
会社の経営者がデザインを決めるとうまくいかない、また現場の営業の人がデザインに関わるとうまくいかないことが多い。さらに、いろいろな人の意見を気にして作ると最大公約数的で平凡なものになり、デザインでインパクトを与えることができない。批判があるくらいのものがあとで評価され、ユーザーに衝撃を与えることが多い。
はっきり言って、会社を経営している人は経営センスがあってもデザインセンスがない場合が多いのだから、デザインに口を出すべきではない。商品が売れるためには経営者ではなくデザインセンスのある人がパッケージや広告を決定すべきなのだ。
「ラバーのパッケージは、ラバー単体でのデザインというよりも、バタフライ・ラバーの集合体としての存在感を重視し、差別化を図ってグローバルにブランド・イメージを浸透させることを目指しました。発表した当初、もちろん『いいね』というご意見もいただきましたが、多くは批判的な声でした(笑)」(山松)
「たとえ経営者であっても、デザイナーが生み出したデザインに手を加えない。これを社内にどう説明するのか考えました。私は最終案までの紆余曲折を間近で見てきたので、このデザインを見た時は感動的でした。ただ、初見だけでは受け入れられづらいだろうと思いました」(大澤)
試行錯誤しながらバタフライのラバーパッケージは一新された。つまり歴史もあり、ユーザーに親しまれていた古いパッケージを捨てたのだ。そしてブランドイメージを独自に作っていく「ブランディング」に重きを置く。たとえば卓球王国の本誌でもタマスは商品広告ではなく、ブランディングとしてのイメージ広告を展開している。
タマスの今までの価格改訂、オープン価格の採用、パッケージの一新などは、アクションを起こした当初はショップやユーザーにはことごとく不評だった。ところが、1年経ち、2年経つと、不評だったものが好評に変わることもあるし、多くの人が理解を示すようになる。それは短期的に起こる批判や買い控えを予想しつつ、この会社は中長期的な戦略で動いているということだ。
「タマスは叩かれやすいメーカーになっているのはわかっています。グローバル企業として、世界に目を向けた経営と商売の環境が変わっている。その環境に適合することはこれからも続けていく」(山松)
バタフライは世界のトップブランドとしての誇りと歴史を保ちつつ激変する市場に対応しようと模索する。古いバタフライは終わったのだ。
蝶は再び蛹から羽化して飛ぼうとしている。新しいバタフライはどこに飛んでいくのだろう。 (文中敬称略) ■
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別冊『卓球グッズ2016』で、「バタフライは終わりか。それとも始まりか」という衝撃的なタイトルをつけ、世に出してから5年が経った。
この時の裏話を少し書いてみよう。
当時、バタフライ(タマス)がヨーロッパでの代理店の仕組みを変え、大ヒンシュクを買っていた。日本でも問屋への出荷価格を大幅に上げ、挙句の果てにはブラックバイヤー撲滅のため、世界標準価格にするという理由で、オープン価格制度を一部の商品に適用し、それまで6000円定価だった大ヒットラバー『テナジー』を市場実勢価格8000円にしていた。
別冊『卓球グッズ2016』の締切も迫り、メイン特集を考えていて、この過激なタイトルを思いついた。今思えば、業界の巨人「タマス」へのささやかな抵抗だったかもしれない。
最初、私が考えたタイトルは「バタフライの終わり」だった。
しかし、タマスは卓球王国にとってメインクライント。その大スポンサーに対して「バタフライの終わり」はさすがにきつすぎるかと逡巡していた。
それでややマイルドにして「バタフライは終わりか。それとも始まりか」というタイトルに変更して、それをある人に会って、表紙のラフデザインを見せた。
その人とは、当時、タマスの相談役だった久保彰太郎さんだった。かつては同社の専務、No.2として経営手腕を発揮した人で、当時は毎月のように食事をともにして、夜中まで様々なことを語り合う卓球界の大先輩であった。
久保さんは2800円だった『スレイバー』『マークV』の時代、1997年に『ブライス』を自ら陣頭指揮をとり開発し、かつ5000円で発売した人で、今のタマスの根幹を作った人でもある。
また久保さんは1950年代後半からの「卓球レポート」の編集長でもあり、「卓球王国」を我々が創刊した頃も、「私ができなかった書店売りの卓球雑誌は素晴らしい。頑張りなさない」と何度も励ましてくれた人でもある。
その久保さんに、別冊のタイトルを見せた。「久保さん、このタイトルで別冊を作りたいんですけど、嫌ですか?」と直接聞いた。
数十秒間、腕を組んだまま黙っていた久保さんは「・・いいですね。面白い」とポツリと言い、「もっと強いタイトルでもいいくらいだ。うちの会社の連中は危機感を持っていないんだから」とも言った。
最初のページのデザインを見せると、「うん、良いデザインだ」とうなずいた。
あれから5年経った。
バタフライは憎らしいほど、健在だ。
『テナジー』は売れ続け、翌年に出した『ロゼナ』もヒット商品になり、2019年に出した『ディグニクス』は9000円前後の市場価格だが、トップ選手の支持を受けている。
愛弟子の大澤さんが2016年9月にタマス社長に就任すると、それを見届けるように翌17年1月に久保さんは急逝した。
久保さんが生きていたら、今の卓球界、そして卓球市場をどう見つめ、何というのだろう。
(卓球王国発行人 今野昇)

2016年の別冊「卓球グッズ」。メイン特集の扉のデザイン
ツイート